
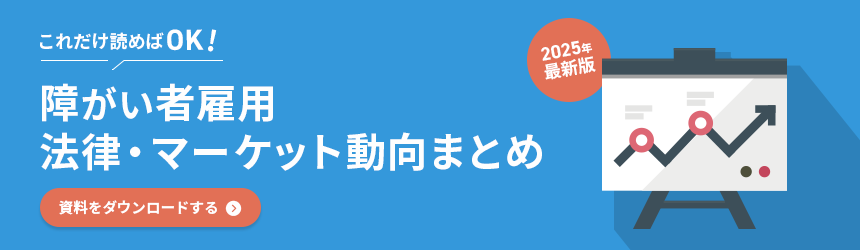
性別や人種、障がいの有無など、さまざまな立場や境遇の人たちが、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境をつくる経営戦略をダイバーシティ経営と呼びます。
近年の、このダイバーシティ経営への注目が世界的に高まっています。この記事では、企業がダイバーシティ経営に取り組むべき理由と実践ポイントを解説します。
ダイバーシティは直訳すると「多様性」を意味し、性別や年齢、人種、障がいの有無など、さまざまな違いのある人々がそれぞれの能力を発揮できる環境のことを指します。この多様性には、性別や人種などの目に見える表層的ダイバーシティのほか、価値観や経歴、宗教観や性自認など、目に見えない深層的ダイバーシティも含まれます。
このダイバーシティの考え方を経営につなげたものが、ダイバーシティ経営です。
経済産業省はダイバーシティ経営を、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義し、取り組みを推進しています。
ダイバーシティ経営を推進する風潮は世界的に広まっており、日本でもその重要性がますます注目されています。
2018年、経済産業省で「ダイバーシティ経営読本」が作成されました。また、2024年には「中小企業のためのダイバーシティ経営」というコンテンツも作成されるなど、国による取り組みは年を追うごとに強化されています。ダイバーシティ経営の注目度は、ここ数年で格段に高くなっているといえます。
では、なぜ近年ダイバーシティ経営が注目されているのでしょうか。ここでは、日本が直面する社会課題から、ダイバーシティ経営が注目される背景を読み解きます。
2025年、日本では団塊世代の全員が75歳以上となりました。諸外国と比較しても少子高齢化の動きが加速している日本では、2040年には全人口の約35%が65歳以上になると推計されています。
少子高齢化の流れは、労働人口の減少に直結します。労働人口が減ると、企業は人手不足の課題に直面することになります。そこで重要となるのが、多様な人材を積極的に活用する姿勢です。
ダイバーシティ経営の観点からそれぞれが活躍できる環境づくりをしていくことで、雇用の間口を広げることが可能です。多様な人材を受け入れることで、自由な発想が生まれ、生産性が向上し、働き手不足の課題解決に対応することができます。
ダイバーシティ経営は、個々の事情や希望に合わせた働き方を実現できる環境整備につながるものです。
正社員雇用・終身雇用などが一般的だった一昔前と比べ、現代の日本人の働き方は実に多様化しています。育児や介護との両立、ライフワークバランスの確保、ダブルワークなど、働く側のニーズもさまざまで、必ずしも正社員雇用にこだわらないと考える人も増えてきました。また、フルリモートワークやサテライトオフィス勤務など、勤務体制も多様化しています。どう働くか、どこで働くかにとらわれず、それぞれの働き方で最大限の能力を引き出せる企業こそ、生き残り、成長していくことができます。
かつて、企業の評価基準といえば、利益や株価などの財務的評価が中心でした。しかし、地球規模での環境課題や社会課題の深刻化をまえに、企業には、それらの課題解決のための責務があるという考え方が広まっています。そこで注目されているのが、ESGやSDGsなどの非財務的な評価指標です。
ESGとは、Environment(環境)・Social(社会)・Governance(企業統治)の頭文字をとった言葉で、この3つの観点からの配慮が企業成長には不可欠という考え方です。また2015年には、ESGの観点をさらにひろげ、地球に暮らす人間ひとりひとりが取り組むべき具体的な目標を設定したSDGs(持続可能な開発目標)が国連で採択されました。
SDGsには17の目標が定められていますが、そのうちの目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う」や目標10「各国内及び各国間の不平等を是正する」を達成するためには、ダイバーシティ経営の観点が不可欠です。世界的・社会的責務を達成するという意味でも、ダイバーシティ経営は重要な取り組みとなります。

ダイバーシティ経営に取り組むことは、企業の社会的責務をまっとうするだけでなく、企業が直面するさまざまな課題を解決することにつながります。ここでは、ダイバーシティ経営が企業にもたらすメリットを4つご紹介します。
企業が長期にわたり成長し続けるためには、イノベーションが不可欠です。イノベーションとは、技術やアイディア、新しいビジネスモデルなど、これまでにない新しい価値を創造する革新的な変化を指します。イノベーションを創出するためには、それまでとは違った価値観や世界観、知識を取り入れる必要があります。
ダイバーシティ経営を実践することで、さまざまな知見や考えをもった人材がともに活躍する環境が整います。新しい価値観が導入されるだけでなく、異なる価値観をもった人材同士でプロジェクトを進めることで、それまでにない全く新しいアイディアが生まれ、生産性の向上も期待できます。
あらゆる人材が活躍できる環境が整えば、それまで雇用に繋がらなかった人材にも活躍の場を提供でき、雇用の間口は大きく広がります。雇用の間口を広げることは、加速していく少子高齢化と、それにともなう人材不足という課題を打破する有効な方法です。
ただし、単に間口を広げるだけでは企業の成長は見込めません。広げた間口で雇用した人材が能力を発揮できるダイバーシティ経営があってこそ、人材不足という課題を解決しつつ、企業が成長できる状態がつくれるのです。
実際、全正社員のうち女性正社員の割合が高い企業や、全女性従業員のうち正社員の割合が高い企業など、ダイバーシティ経営に関する取り組みがさかんな企業ほど新卒採用の充足率が高いという相関関係もみられています。
参照:株式会社博報堂 令和6年度中小企業実態調査事業調査報告書
また、障がい者雇用に目を向けると、間口を広げて知的障がいのある方を受け入れた企業では、仕事の進め方や教え方を職場全体で話し合う中で、 社内のコミュニケーションが活性化し、職場の雰囲気も改善しました。その結果、社員の笑顔が増えて接客の質が向上し、顧客満足度の向上につながったという事例もあります。
性別や年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、あらゆる人材が活躍していることをアピールすることは、多様性の時代における企業ブランディングの一端も担います。
特に障がい者雇用では法定雇用率が定められており、企業の社会的義務として広く認知されているうえ、その取り組み状況が企業評価の一因となっています。障がい者雇用を含むダイバーシティ経営の実践は、社会的責任を果たす企業としてのイメージ向上につながります。
企業成長に不可欠なESGの認知度が広まる一方、SDGsの達成目標期限は2030年に迫っています。そのなかで、持続可能な世界をつくる責任は企業にもあるという認識が広がっています。
これからの時代を生き抜く企業には、ESGやSDGsへの対応が不可欠です。ダイバーシティ経営を実践することは、このふたつの考え方と目標に直結しており、ひいては企業の経済成長にもつながります。
ダイバーシティ経営は企業の競争力強化のための重要な取り組みです。日本経済の持続的成長にとっても不可欠であるとされ、経済産業省でも推進の取り組みがおこなわれています。
日本では、平成24年度から令和2年度にかけ、ダイバーシティ経営に取り組む企業を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」という制度がありました。多様な人材の活躍への取り組みやその成果を評価する制度です。そのほか、女性活躍推進に優れた取り組みをしている上場企業を選定する「なでしこ銘柄」制度などを通して、ダイバーシティ経営への優秀な取り組みを広く発信しています。
ここでは、日本企業のダイバーシティ経営の取り組み状況と、具体的な取り組み内容の一例をご紹介します。
博報堂が発表した「令和6年度中小企業実態調査事業(ダイバーシティ経営の実践に向けた労働市場における実態調査およびインクルーシブな企業風土の醸成に関する調査事業)」によると、日本の中小・中堅企業のダイバーシティ経営に関する進捗は、企業間で大きな格差があることが明らかになっています。
例えば、女性従業員比率が0%の企業数は一社もありませんが、女性役員比率が0%の企業は全体の半数以上になります。役職があがるほど女性の割合が減っていく傾向にあり、ダイバーシティ経営の観点からは改善の余地があるポイントとなっています。
また、男性育休取得率をみると、取得率50%の企業が28.1%ある一方、52.0%の企業は取得率0%であり、取り組みの格差が大きい事がわかります。取り組みの数値が高い企業であっても、ダイバーシティ経営推進に困難を感じていない企業は1社もなく、それぞれが課題を抱えながら取り組みをしている状況です。
そのほか、有給取得の取得促進や障がい者雇用の推進など、ダイバーシティ経営への取り組みはさまざまです。精力的な取り組みが評価される企業がある一方、取り組みに手付かずな企業もあり、社会全体としてさらなる取り組み強化が求められます。
参照:株式会社博報堂|令和6年度中小企業実態調査事業(ダイバーシティ経営の実践に向けた労働市場における実態調査およびインクルーシブな企業風土の醸成に関する調査事業)
2018年4月に経済産業省より公表された「適材適所のススメ」より、いくつかの事例をご紹介します。
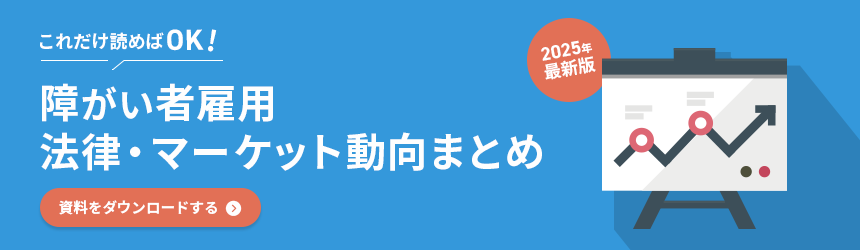

ダイバーシティ経営は企業の長期的な成長に欠かせない取り組みであり、今後ますます積極的に取り組んでいくことが求められますが、経営者の取り組み、人事管理制度の整備、現場管理職の取り組みを3つセットで進めることが必須です。しかし、今までにない取り組みをすることでスタートに悩んでいる企業の担当者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、企業のためのダイバーシティ経営実践ポイントを解説します。
導入にあたっては、まず全体像をつくり、そこへ向けて段階的に取り組みを進めていく必要があります。以下のようなステップで進めてみましょう。
これらの一連の流れでPDCAサイクルをまわします。効果検証と改善を繰り返すことで、ダイバーシティ経営の質を高めていくことが重要となります。
ダイバーシティ経営が目指すのは、働く人それぞれが能力を発揮できる環境の実現であり、そのためには社内理解が不可欠です。経営者は自社の目指す場所やその実現のための取り組みを社内にオープンにし、理解を深める必要があります。
社員の理解を深める際は、社内研修やワークショップが効果的です。ダイバーシティ経営の基礎知識とそれが求められる理由を従業員目線まで落とし込み解説します。その後、普段の仕事のなかで感じるダイバーシティ経営の課題や、それをもとにした理想像、実現に向けたアクションを話し合うなど、社員が主体となった対話の場を設けることが理想的です。
ダイバーシティ経営の推進には、社員一人ひとりの考え方が何より重要です。経営陣だけで進めるのではなく、会社が一体となって理想の実現に取り組んでいくことが、成功のカギとなります。
経済産業省では、社内理解を深めるためのダイバーシティ・コンパスワークショップのノウハウをマニュアルにして公開しています。事前課題配布資料や投影資料などもあるので、積極的に活用しましょう。
エスプールプラスでは、障がい者雇用に取り組む企業向けに農園型障がい者雇用支援サービスを提供しています。
多様な人材の活躍を目指すダイバーシティ経営において、障がい者雇用は欠かすことのできない視点です。義務的な雇用ではなく、障がい者と健常者が互いによい影響を与え合えることが、障がい者雇用の理想となります。
エスプールプラスが提供しているサービスは、大きく分けて以下の2つです。
●障がいのある方のご紹介
●就労の場となる農園の区画のお貸出し
エスプールプラスが貸し出す農園は全国58か所にあります(令和7年9月現在)。農園では、障がい者と管理者が農園を利用する企業と直接雇用契約を結び、チームで作業にあたっています。知的障がい者のほか、発達障がい者、定着率の低い傾向にある精神障がい者も長く楽しく働き続けられる仕組みです。1年後の定着率は92%以上と、障がい者雇用においては非常に高い水準となっています。
農園数が多いため、本社と物理的距離が近い農園を活用できることも利点のひとつ。障がいのある方でも安心安全に働くことができ、かつ本社の従業員と交流しやすいことが特徴です。実際に社員による農園訪問は多く行われています。また、農園で収穫された野菜は福利厚生として本社で販売されることがポピュラーです。なかには、障がい者スタッフと本社社員が野菜に添えたメッセージカードなどでやり取りを行っている企業もあります。こうした相互交流や野菜を通じたやりとりが、障がい者雇用ではたらく人のやりがいにつながります。
また本社社員にとっては、障がいのある方をより身近に感じることができ、ノーマライゼーション意識の向上も実現します。まさに、互いの良さを認め合いながら全ての社員が活躍できるダイバーシティ経営の実践に繋がるのです。
ダイバーシティ&インクルージョンの視点から考える障がい者雇用についてのセミナーを開催しています。
セミナー詳細・申込ページはこちら >
ダイバーシティ経営は、企業の課題解決や世界が直面している長期的な問題解決につながる重要な取り組みです。日本においても経済産業省を中心にダイバーシティ経営の推進が叫ばれていますが、その取り組みの状況は企業ごとに大きな違いがあるのが現状です。
エスプールプラスが提供する障がい者雇用支援サービスでは、貸し農園の活用によって障がいのある方が能力を発揮できる環境を提供し、ノーマライゼーション意識の向上をサポートしています。ダイバーシティ経営への取り組みの一環として重要な取り組みである障がい者雇用。その取り組みにお悩みの際は、ぜひエスプールプラスの障がい者支援サービスの活用をご検討ください。



世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用...