
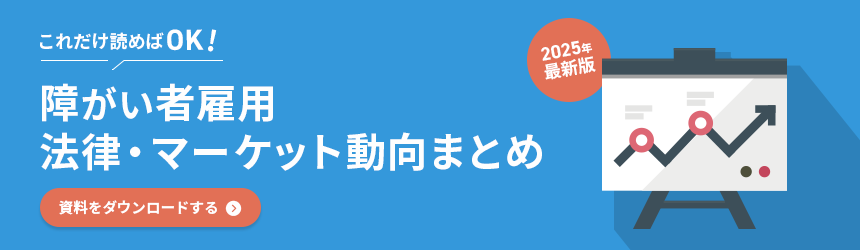
近年、企業経営の現場でダイバーシティという言葉を耳にする機会が増えています。
経営におけるダイバーシティとは、性別・年齢・人種・障がいの有無など、さまざまな特性や背景を抱える人が、それぞれの力を発揮できる 環境を構築することを意味します。ダイバーシティの推進は、企業の成長に大きな効果をもたらします。
この記事では、ダイバーシティ推進のメリットや具体的な取り組みの方法について解説します。
「ダイバーシティ(diversity)」とは、多様性を表す言葉で、 さまざまな人材が活躍できるようにする考え方です。 ここでいう多様性には、性別、年齢、人種、障がいの有無外だけでなく、人生観や宗教的な考え方、性自認や性的指向など、目には見えにくい違いも含まれます。
こうした多様性を企業経営に活かすことを、「ダイバーシティ経営」と呼びます。企業が多様な人材を受け入れ、それぞれが持つ能力や個性 を活かせる仕組みを整えることで、組織全体の 生産性の向上や競争力の強化につながります。
企業経営 におけるダイバーシティとは、多様な人材を受け入れる段階を指します。「障がいがあるから雇用できない」「国籍が異なるから不安」などといった雇用における固定観念を見直し、多様な人材が働ける環境を整えることがダイバーシティ推進の第一歩です。
一方、D&Iとは、「Diversity(多様性)&Inclusion(包摂)」の略です。「Inclusion」は、多様な人材が組織の中で互いに認め合い、それぞれの能力を十分に発揮できる環境をつくることを意味します。たとえば、公平な人事評価制度の整備や、障がいのある方も働きやすい職場づくり、企業全体でのノーマライゼーション意識の醸成などが含まれます。
ダイバーシティが「多様性のある人材を受け入れる入り口」だとすれば、インクルージョンは「その多様性を活かすプロセス」です。企業がダイバーシティ経営を成功させ、組織の持続的な成長を目指すためには、この両方をセットで推進していくことが不可欠となります。

近年、ダイバーシティは企業経営において注目を集めるテーマです。行政もダイバーシティの推進を積極的に支援しており、障がい者雇用の促進や女性の社会進出、多様な働き方の実現、幅広い取り組みを行っています。また、経済産業省は、「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」などを通じて 、単なる法令遵守にとどまらず、 企業が多様性を活かした経営を実現し、競争力を高めていくことを後押ししています。ここからは、ダイバーシティがこのように重要視される理由を4つご紹介します。
日本では、労働人口が減少の一途をたどっており、多くの企業が目の前の深刻な課題として実感しています。
戦後の第一次ベビーブームで生まれた、いわゆる団塊の世代は、2025年に全員が75歳を迎え、高齢化が進んでいます。さらに少子化も加わり、今までどおりの雇用形態を継続していくことは困難な状況となっています。
こうした人材不足の中で、多様な人材が共に働く環境を作っていくことは、これからの企業成長に不可欠な取り組みです。これがまさにダイバーシティの考え方であり、ここに労働力・人材不足の課題を解決する糸口があるのです。
かつては正社員としての終身雇用が一般的でしたが、今は働き方の多様化が進んでいます。育児や介護との両立や、ワークライフバランスの確保、副業(兼業)の希望など、働く人の事情や価値観は多様化しています。そうした背景から、自分に合った働き方を選ぶ人も増えてきました。
そのため、テレワークやサテライトオフィスの活用、フレックスタイム制の導入など、働く場所や時間に柔軟性を持たせる企業も増えています。「どこで・どのように働くか」に縛られることなく、社員一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できる環境を整えている企業こそ、持続的な成長を遂げられる時代となっています。
ダイバーシティは、こうした多様な働き方を実現する基盤となる考え方です。
国連によってSDGs(持続可能な開発目標)が採択され、企業には、ただ利益を生み出すだけでなく、社会や世界に対する責任を全うすることも求められる時代となりました。SDGsの目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う」や、目標10「各国内及び各国間の不平等を是正する」などを達成するためには、雇用におけるダイバーシティの視点が欠かせません
また、前項で述べた人材不足などの背景を踏まえ、近年では企業の「人的資本」に対して、投資家の関心が高まっています。
投資家は企業に対し、自社の成長のためにどのような人材を 確保し、どのように能力を発揮できるようにしているのか、その戦略を開示する ことを求めるようになっています。
このように、企業が人材に関する情報を可視化し、外部に向けて積極的に発信することを「人的資本開示」といいます。経営者自らの言葉で説明する姿勢も重視される傾向にあり、人的資本開示は企業評価の重要な要素となりつつあります。
こういった背景のもと、企業にはダイバーシティ推進が一層求められるようになってきています。
ダイバーシティ推進に積極的に取り組んでいる企業は、高い社会的評価を得やすくなり、ひいては企業ブランドの向上につながります。わかりやすいブランドイメージは商品やサービスの購買意欲を高めるだけでなく、求職者にとっても魅力的な企業に映ります。そのため採用活動も多様で優秀な人材を集めやすくなるのです。
これらの成果は、企業の長期的成長において大きな推進力となるでしょう。
ダイバーシティの推進はいまや国を挙げて取り組むべき課題となっています。ここでは、行政が進める代表的なダイバーシティ推進施策を2つご紹介します。
経済産業省は平成29年3月、「ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン」を公表しました(平成30年6月改定)。
ダイバーシティ2.0とは「多様な属性の違いを活かし、個々の人材の能力を最大限引き出すことにより、 付加価値を生み出し続ける企業を目指して、 全社的かつ継続的に進めていく経営上の取組」と定義され、取り組みのポイントとして以下の4つのポイントが示されています。
また、具体的な取り組みの手順のほか、実践のための7つのアクションも提示されており、企業がダイバーシティ推進に実際に取り組むための指南書的存在となっています。
厚生労働省では令和6年度、職場におけるダイバーシティ調査・推進事業において、「多様な人材が働きやすい職場環境整備に関するアンケート調査」を実施しました。
調査では、一般の労働者に加え、性的マイノリティの方々を対象とした実態調査も行われました。 調査結果の概要、就労する性的マイノリティ調査結果の報告書のほか、性的マイノリティに関する実際の取り組み事例も公開されています。
これらの情報は、企業が多様な人材を受け入れる環境を整備する上での参考資料として活用できます。
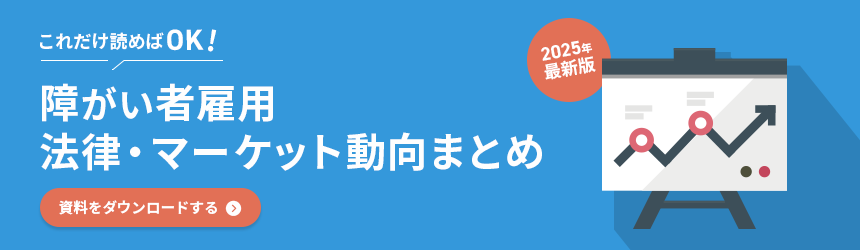

ダイバーシティの推進は、企業とそこで働く従業員に大きなメリットをもたらします。その具体的なメリットを4つご紹介します。
前述のとおり、ダイバーシティ経営は労働力不足の時代の人材確保に非常に有効な手段です。多様な人材を受け入れる 環境が整っていれば、それまでの雇用の固定観念にとらわれず 、採用の間口を広げることが可能になります 。
働く従業員にとっても、自身の能力が発揮できていると感じられる職場は働きがいやモチベーション の向上につながり、長期的な活躍や新たなキャリア形成のチャンスも生まれやすくなります。結果として、従業員の定着率が向上し、企業にとっては人材不足という課題の根本的な解決にもつながっていきます。
ダイバーシティが推進された環境ではあらゆる立場の従業員が活躍でき、多様な働き方が認められます。「自分が尊重されている」という実感を得やすく、仕事への意欲が向上します。
また、時短勤務や副業など、さまざまな働き方が選択できることも、ダイバーシティ推進の魅力の一つです。こうした働き方の選択は ワークライフバランスの実現を後押しし、従業員がより安心して前向きに働ける職場づくりに貢献します。
現代社会 では、顧客や市場のニーズも複雑かつ多様化しています。そのため、今までの画一的な商品やサービスでは顧客の期待に応えることが難しくなってきました。 それぞれの価値観に寄り沿ったパーソナライズされたサービスが重視される今、企業側にも多様な視点や感性を持つことが求められるようになっています。
そのためにも、社内に多様な背景を持つ人材が存在し、それぞれの意見や考え方が活かされる組織づくりが不可欠です。
ダイバーシティの推進は、こうした市場ニーズへの対応力を高めるうえで、大きな力となります。
ダイバーシティへの取り組みを人的資本の一環として開示することは、企業の長期的な成長力を示す指標の一つとして評価されます。そうした評価は投資家や取引先からの信頼向上につながり、企業が成長していく際の一助となります。
ダイバーシティの推進は企業が取り組むべき重要なテーマですが、これまでと異なる取り組みには難しさが伴うものです。ここでは、ダイバーシティ推進において企業が直面しやすい課題を3つご紹介します。
企業の風土は、それまでの伝統や企業の歩みによって育まれてきたものです。一見すると 風通しのよい柔軟な社風であっても、そのなかに固定観念が残っていることは珍しくありません。
ダイバーシティの推進は、単にルールを定めればいいというものではありません。組織文化は社内の習慣や価値観の集合体であり、それを変えることに対して心理的・組織的な抵抗が生じることもしばしばあります。だからこそ、ルールの整備だけでなく、働く人の意識や行動の変化を通じて、少しずつ文化を育てていくことが大切です。
企業の方針や風土は、経営層や管理職の言動・方針に大きく影響されます。そのため、経営層や管理職がダイバーシティの意義を十分に理解し、日々のマネジメントの中で体現していくことが重要です。 一方で、ダイバーシティへの理解が不十分な場合、現場の取り組みが十分に活かされず、組織全体としての浸透に時間がかかることもあります。
経営層が率先して理解を深め行動で示していくことが、職場の意識を変える大きな一歩となります。
ダイバーシティの取り組みは、数値だけで成果を 測れるものではありません。掲げられる数値目標としては、女性管理職の割合、障がい者の法定雇用率の達成などがありますが、数字にこだわってしまうと本質的な取り組みである「多様な人が活躍する環境づくり」から離れてしまう恐れがあります。
ダイバーシティの本質は組織文化や風土の改革にあります。こういった数値目標化の難しさが、ダイバーシティ推進の壁となる場合があります。

ダイバーシティの推進は、いくつかのポイントを押さえることで取り組みやすくなります。そのポイントを5つご紹介します。
ダイバーシティ推進で大きな鍵を握るのは、経営層のリーダーシップです。なぜなら、ダイバーシティの推進は組織文化や風土の改革が伴うものであり、その文化や風土の基盤となるのは経営層の方針や考え方であるからです。
したがって、まずは経営層がダイバーシティの推進にコミットメントし、取り組みをリードしていく必要があります。経営計画の中で多様性推進を位置づけたり、多様な人材が活躍できる仕組みを整備したりすることが効果的です。
また、現場でおこなわれるダイバーシティ推進の取り組みを経営層が確認する姿勢も大切です。
ダイバーシティの取り組みは、数値だけで測りにくいものではありますが、明確な目標と指標を設定することは重要です。たとえば、女性役員の比率、女性の採用比率、男女別の育児休業取得率、外国人従業員の人数、障がいを持った従業員の比率など、あらゆる観点での到達目標を設定してみましょう。
ただし、これらの数値はあくまで指標であることを念頭におかなくてはなりません。数字の達成を求めるあまり表層的な取り組みにならないよう、十分に注意しながら取り組みを進めていく必要があります。
単に多様な人材を採用するだけでは、真のダイバーシティとは言えません。多様な人材を活かすための環境づくり(D&I)を同時に行わなければ、逆に多様性が十分に活かされない恐れがあります。
その具体策として挙げられるのが、人事制度や働き方の見直しです。人事制度においては、年功序列的な人事システムの見直しや適材適所の人材配置などがあります。働き方の面では、フレックスタイム制や在宅勤務などの制度の整備、出産・育児・介護に対応する休暇制度の充実などが効果的です。
従業員一人ひとりのライフプランや価値観を尊重し、それぞれの能力を発揮しやすい環境を整えていくことが大切です。
従業員の教育とそれによって得られる意識の変化は、ダイバーシティ推進において最も重要な土壌となります。多様な価値観や性的指向、障がい特性などについて理解を深め、互いの違いを尊重し合うことが、誰もが働きやすい環境づくりの第一歩です。
そのためには、 多様な人材が共に働くことの意義やメリットを学び、自分自身の働き方やかかわり方と結び付けて考える機会が大切です。こうした学びを通して、違いを活かすことが企業の成長につながるのだという認識を深めていくことが必要です。
ダイバーシティの主役は働く人たちです。管理職や担当者は、実際に働いている人たちがどう感じているか、一人ひとりの声に耳を傾け続ける必要があります。現状を定期的に可視化し、改善点があればそれを特定して次のアクションにつなげる。こうしたサイクルを回し続けていくことで、ダイバーシティの取り組みは徐々に組織文化として定着していきます。
ダイバーシティとは多様な人材が共に活躍する環境を指します。人材不足をはじめとした企業の課題を解決すると同時に、誰もが自分らしく働ける社会の実現にもつながる取り組みです。
こうしたダイバーシティの推進は国全体としても力を入れて進められています。
ダイバーシティの推進においては、経営陣の積極的な姿勢が欠かせません。その姿勢が社員一人ひとりの意識や行動の変化へと広がっていきます。 。ダイバーシティが社内に浸透している企業は、外から見ても持続的に成長できる企業とみなされ、消費者の購買意欲や取引先からの信頼感の向上にもつながるのです。
今回解説したダイバーシティの概要や推進の方法を押さえながら、ぜひダイバーシティの定着と継続を目指していきましょう。


世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用...