

近年、障がい者雇用の新たな形として、本社や支社以外の場所で働く「サテライト型」の就労スタイルが注目されています。特に、障がいのある方が働きやすい環境を整備した「サテライトオフィス」を活用する支援サービスは、企業にとって人材確保や初期コスト抑制のメリットがあり、働く障がい者にとっても手厚いサポートの下で安心して就労できるという利点があります。
一方で、コミュニケーションの課題や、画一的な業務内容になりやすいといった側面も指摘されています。
この記事では、サテライトオフィス型の障がい者雇用支援サービスの概要、メリット・デメリットについて解説します。
サテライト型の障がい者雇用とは、障がいのある方が本社や主要な事業所ではなく、通勤しやすい場所や、特性に合った働きやすい環境が整備された別の拠点で就労する形態を指します。
「サテライトオフィス型」の障がい者雇用支援サービスは、バリアフリー設備が整っていたり、支援員が常駐していたりするなど、障がいのある方が安心して働けるように特化したオフィスを利用するものです。通勤距離やオフィス環境への適応に課題がある方でも、職場定着が期待できる方法として導入が進んでいます。
一般的にサテライトオフィスとは、本社や支社など本来の配属先以外にある就業可能なオフィスのことを指し、従業員の通勤負担軽減などを目的に活用されます。本社等から離れて働くためテレワークの一形態と捉えられますが、在宅勤務に比べて雇用管理やオンオフの切り替えがしやすいという特徴があります。
サテライトオフィス型の障がい者雇用は、2019年に初めて厚生労働省による委託事業がおこなわれた、比較的新しい雇用方法です。それまでの障がい者雇用にあった課題を解決できる方法として、徐々に注目を集めると同時に、サテライトオフィス型の障がい者雇用支援サービスが増えてきています。このようなサービスについて、雇用側、就労側それぞれからみたメリットをいくつかご紹介します。
サテライトオフィス型の障がい者雇用は、通勤やバリアフリーな就労環境など、さまざまな理由から通常のオフィス勤務が難しい障がい者の雇用が可能になる場合があります。従来は雇用が難しかった障がいのある方々にも、就労の機会を提供できる可能性があります。
障がい者が働きやすい環境と雇用管理体制が一体となって整えられている点が、障がい者向けサテライトオフィスの大きな特徴です。この特別な配慮があるからこそ、一般的なオフィスに比べて高いレベルで働きやすさを実感でき 、雇用の安定化や離職率の低減が期待されています。
障がい者雇用に対応するため、会社の施設や設備の整備を必要とするケースもあるでしょう。そのためのコストは決して小さいものではありません。
サテライト型オフィスを活用する場合、初期費用や月額管理費はかかりますが、施設や設備の整備を行う場合と比べると、安価に済ませることができます。
障がい者向けのサテライトオフィスは障がい者が利用することを前提として設計されているため、バリアフリー環境が整っています。段差がないことはもちろん、入り口の幅や机の高さなどの配慮も行き届いています。
また、支援員が常駐しているのが一般的で、安心してさまざまな相談をすることができます。
障がい者が企業で働く場合、障がい特性上必要とする合理的配慮を求めることは正当な権利としてありますが、言い出しにくいという方もいるでしょう。最初からバリアフリー環境が整っているサテライトオフィスであれば、その心配も少なく就労できます。
サテライトオフィスが自宅から離れた都市部ではなく居住地に近い場合は、通勤の負担軽減にもつながります。通常のオフィスが都市部にあり、通勤が困難な場合でも、サテライトオフィスが近くにあれば就業可能になります。また、在宅勤務を希望していても、十分な通信環境を整備できない場合、通信環境が整備されたサテライトオフィスに通うことで業務が可能になります。
多くのメリットを持つサテライトオフィス型の障がい者雇用ですが、導入・運用にあたっては、企業側・障がい者側双方にとってのデメリットやリスクについて、十分に理解しておく必要があります。

サテライトオフィスで就業する場合、業務はリモートワークとなります。そのため本社や支社の社員と直接会う機会が減り、コミュニケーションがとりにくくなる可能性があります。
コミュニケーションがとれていないと、仕事の進行が遅れたり、認識の食い違いが生じたりして、業務に支障がでるほか、会社への帰属意識も生まれにくいです。そうならないためにも、就業中は手軽にコミュニケーションがとれるようなシステムやルールを導入しておく必要があります。
新たに雇用した障がいのある社員がサテライトオフィスのみで仕事をしていると、ほかの社員は障がいのある社員と関わる機会がなくなってしまいます。その状態だと、障がいのある方との相互理解が進みにくくなります。結果として、業務の拡大を進めたくても社内の協力者が表れにくくなります。
会社全体のD&Iを推進していくためには、障がいの有無に関わらず、社員同士の交流が大切です。
働きやすさが魅力のサテライトオフィスでの業務ですが、会社から離れた場所で働く分、比較的単純な業務内容ばかりを任されるケースが多くなります。簡単な業務をしっかり確実にこなしていけば徐々に任せてもらえる業務の範囲も広がりますが、短時間でのキャリアアップは難しい傾向にあります。
サテライトオフィス勤務でも社員であることは間違いないですが、本社や支社に出勤する機会が少ないため、人によっては勤務する会社の社員としての意識を持ちにくくなってしまう可能性もあります。会社の一員としての意識をしっかりと持って働きたい方は、可能であれば出社とサテライトオフィスの活用を組み合わせた就業スタイルにするのも一つの方法です。

障がい者雇用を進める上で、サテライトオフィス型を含め外部の支援を活用することは有効な選択肢の一つです。しかし、その活用方法によっては、障がい者雇用の本来の趣旨から離れてしまう可能性も指摘されています。
厚生労働省の労働政策審議会(2023年4月)でも、障がい者雇用に関する外部サービス利用のあり方について、以下のような点が議論されました。これは、企業が外部サービスを活用する際に、常に念頭に置くべき重要な視点と言えます。
国が掲げる「共生社会の実現」という理念は、障がいの有無に関わらず、誰もが人格と個性を尊重され、支え合いながら活躍できる社会を目指すものです。企業には、法定雇用率の達成はもちろんのこと、この理念に基づき、障がいのある社員が自社の一員としてその能力を発揮し、他の社員と共に成長していけるような環境を主体的に創り上げていく責務があります。
サテライトオフィスや農園型といった外部の支援サービスの活用において重要なのは、これらのサービスを単なる負担軽減や雇用率達成の「受け皿」として捉えるのではなく、障がいのある社員が活躍し、企業に貢献するための手段として、企業自身が主体的に関与し、最大限に活用していく姿勢です。安易な導入や「丸投げ」ではなく、理念に基づいた適切な活用が求められています。
これまで見てきたサテライトオフィス型のと同様に、コミュニケーションや業務内容の多様性、企業への貢献といった課題に対応するアプローチとして、「農園型」の障がい者雇用支援サービスがあります。
その代表例が、エスプールプラスが運営する企業向け貸し農園を活用した障がい者雇用支援サービスです。障がい者の就労場所は、「わーくはぴねす農園」。障がい者を雇用する企業が農園を借り、その農園で障がい者が働く仕組みです。障がい者雇用のモデルのひとつとして、多くの企業が活用しています。
このように、農園型は、サテライトオフィス型が抱える課題の一部を補い、障がい者雇用の本来の理念にも合致しやすいモデルとして、多くの企業に導入されています。
「わーくはぴねす農園」について、さらに詳しい情報や導入事例にご興味をお持ちの企業様は、ぜひ以下のページをご覧ください。
農園型障がい者雇用について詳しく知りたい方は、以下のページも参考にしてください。
サテライトオフィス型の障がい者雇用サービス は、障がいのある方の働きやすさを実現し、企業の雇用ハードルを下げる有効な手段の一つです。しかし、コミュニケーション不足や帰属意識の低下、雇用率達成のみが目的化してしまうリスクといった課題も存在します。
大切なのは、障がい者雇用の本来の目的を見失わず、障がいのある社員が企業の一員として、その能力を発揮し、共に成長できる環境をどう構築するか、という視点です。
自社にとって、そして障がいのある社員にとって、より良い雇用の形を実現しましょう。
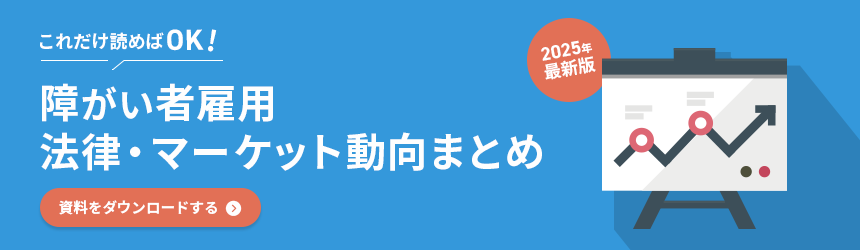


世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用...