
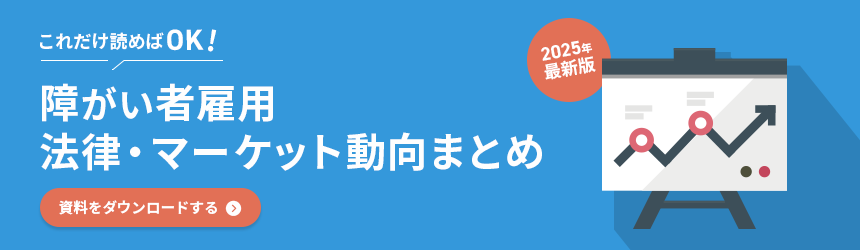
障がい者雇用は、障害者雇用促進法で定められています。一定以上の規模の企業には障がい者の雇用が義務付けられており、企業の社会的責任の一つとして認識されています。
障がい者雇用も一般雇用も、採用面接や採用試験を経て採用される点は同じですが、障害者雇用率制度における障がい者雇用では、障がいのある方がその特性前提として採用されます。採用の段階で企業に障がい特性を伝えることで、入職後にその特性への配慮を受けやすくなります。通院や休憩などへの融通も効きやすいケースが多いようです。たとえば、通院のための勤務時間の調整や、休憩の取り方など、柔軟に対応してもらえる場合が多くあります。
一方、障がいがありながら一般雇用で採用される方もいます。その中でも、障がいがあることを伏せて一般採用で就職する場合、入職してから働きにくさを感じても、伏せたままだと、それを解消するための配慮を周囲に求めづらくなります。
障がい者雇用について詳しくは下記をご覧ください。
「障害者雇用とは?条件や支援制度などを解説」
障がい者雇用にあたっては、企業に対して障がい者雇用率が設定されています。法定雇用率が2.5%の場合、雇用義務のある民間企業は従業員を40人以上雇用している企業となります。この雇用率は段階的に引き上げられており、民間企業における法定雇用率は今後以下の通り引き上げられることが決まっています。
| 2023年度まで | 2024年4月 | 2026年7月 | |
|---|---|---|---|
| 法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
これまで雇用義務がなかった企業であっても、法定雇用率の引き上げによって雇用義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。
企業が障がい者雇用を行うメリットの大きな点は、法律で定められている障害者雇用率を達成できることです。しかし、法律を遵守する以外にも、障がい者雇用を行うメリットはあります。
企業が社会で活動していくためには、社会からの信頼が重要です。
企業が自社の利益だけを追求するのではなく、すべてのステークホルダー(消費者や投資家に加え社会全体の利害関係者)を視野に入れ、よりよい社会づくりを目指す活動のことを、CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)といいます。
企業によっては、CSR報告書の中で、ダイバーシティ推進の一環として、女性やシニア、外国人の活躍の場とともに、障がい者雇用についての取り組みについて記載していることも多くあります。障がい者雇用率を達成し、障がい者が活躍している企業であると示すことは、社会的責任を果たしていることを明らかにすることにもつながります。
より具体的には、法定雇用率の達成状況に応じて公共の競争入札案件で加点となる事例や、ユニクロを運営するファーストリテイリング社のように、障がい者が店舗づくりや売上増大に重要な役割を担っている事例もあります。
(外部リンク:ファーストリテイリングD&Iページ)
近年、多様性のある会社づくりの重要性が世界的に注目されています。多様な人材を雇用し、それぞれがもつ能力を発揮できる環境を整えることで、あらたな発想や今までにない価値を生むことが期待できます。
ここでいう多様性には、性別、年齢、人種、国籍のほか、キャリアや働き方なども含まれます。
障がい者雇用の推進は、多様性のある会社づくりにつながるだけではなく、障がいのある方に関わる従業員を中心に、業務の指示や作業手順をわかりやすく伝えようと配慮する姿勢が生まれます。そのような姿勢が全社に広がり、組織全体のコミュニケーションが活発化し、安心して発言・行動ができる、心理的安全性の高い職場づくりにつながります。その結果、企業全体の生産性の向上が期待できます。
日本の労働力不足は年々深刻化しています。この先は、いかに多様な人材を確保し能力を発揮させられるかという点が、企業が生き残っていくために大切な視点となります。
シニアや短時間勤務の方の雇用が注目されていますが、障がい者雇用も同様、労働力不足解消につながる貴重な戦力です。障がい者雇用に積極的に取り組み、多様な人材がともに働くノウハウを積むことは、会社の多様性だけでなく、来たるべき人材不足に対応する力をつけることにもつながるのです。
多くの企業では、障がい者を雇用することをきっかけに社内業務の見直しをおこない、業務を切り出しています。業務を見直すことが、業務を最適化したり効率化をはかったりする機会となることも珍しくありません。
既存の業務や組織を変えていく必要は感じていても、実際に見直しをかけるには社内の調整が大変で、手をつけられていなかったかもしれません。また、長い期間、同じようなフローで業務にあたっている場合、商品・サービスの品質向上、コスト削減、組織の体質改善などの点で変化が必要なことも少なくありません。
そのような業務や業務フローを全体に見直し、再設計すれば、業務の効率を高めることができます。そして、その中に障がい者が行う業務を作り出すこともできるのです。
障がい者雇用に関する企業への金銭的な支援として、助成金や、地方自治体からの奨励金などがあります。障がい者雇用に関連する税制優遇措置については、「障がい者雇用で優遇される税金とは?」をご覧ください。
助成金は、障がい者を雇用した時に活用するものがよく知られていますが、その他にも施設や設備のメンテナンス、雇用管理で適切な措置を実施、職業能力開発、職場定着のための措置を実施するなどの場合にも、活用できる助成金があります。
障がい者雇用で、企業がよく活用する助成金には、次のようなものがあります。
企業は、障がい者を雇用することが求められていますが、それが達成できないと障害者雇用納付金の支払いや行政指導、企業名公表が行われます。
障害者雇用納付金制度において、障がい者を雇用することは、「事業主が共同して果たしていくべき責任である」という社会連帯責任の理念に基づいています。そのため、企業間の障がい者雇用にともなう経済的負担の調整を図るべく、国は雇用義務を果たしていない企業から納付金を徴収しています。
法定障害者雇用率を達成していない場合、不足している障がい者1人あたり月5万円が徴収されます。つまり、障がい者雇用が1人不足するごとに年間60万円の雇用納付金を納めなければならないことになります。障がい者雇用の義務は、法定雇用率2.5%の場合、常用雇用40.0人以上の企業に課されますが、雇用納付金の徴収は100人以上の企業が対象となっています。
障がい者雇用の対象となっている企業には、毎年6月1日現在の障がい者の雇用に関する状況をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項 障害者雇用状況報告)。
この報告をもとに、ハローワークは障がい者雇用の状況を把握しますが、雇用率を大幅に下回っている企業に対しては、2年計画の「雇入れ計画作成命令」が発令されることがあります。計画実施後1年時点での雇用状況が悪い場合には雇入れ計画の適正実施勧告が発令され、それでも改善が遅れている場合には行政の特別指導が入ります。
計画の作成や行政指導が入る場合、それに対応するためにはそれなりの時間と労力が必要になります。通常の業務に加えてこの対応をしなくてはいけないのは、企業にとっては大きな負担です。また、行政指導の時点で企業名が公表されることはありませんが、情報が漏れて企業のイメージダウンにつながるリスクもあります。
行政指導によってもなお障がい者雇用の改善がみられない場合は、企業名が公表されます。最近では、令和5年3月に5社の企業名が公表され、そのうち1社は行政指導にもかかわらず雇用状況の改善がみられないとして、令和6年3月に再公表されました。
参照:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」
企業名が公表されることは、ブランドイメージの毀損に直結します。また、その企業と取引をしている企業のイメージが悪くなる可能性もあり、取引の解消となるリスクもあるでしょう。
企業名の公開はウェブ上でおこなわれます。一度このような形で企業名が公開されるということは、その後状況が改善されたとしても、過去の情報が誰かの目に留まる可能性がずっとあるということです。一度でも企業名が公表されることは企業にとって大きなデメリットであることを理解しておきましょう。
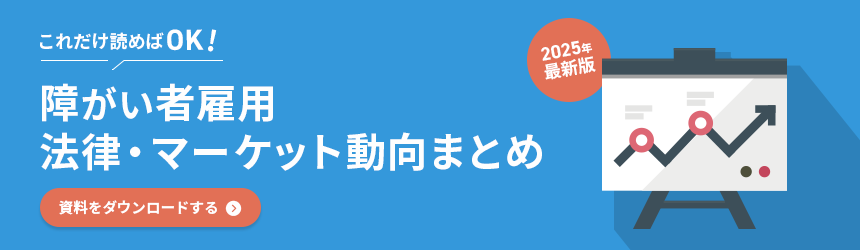
障がい者雇用に取り組んだ際に得られるメリットは大きい反面、取り組まない場合に被るデメリットは企業の経営に悪影響を及ぼすことが予想されます。
障がい者雇用に取り組むための手間やスタッフの人件費などが気になる方もいるかもしれませんが、障がい者雇用への取り組みは、企業が持続的に成長していくために必要不可欠なものと捉えるべきです。続けていくことでノウハウをためれば、独自の障がい者雇用スタイルを確立していくことも可能でしょう。
障がいの有無に関わらず、多様な人材が活躍できる会社をつくるメリットは、他にはかえられない企業の宝となるはずです。
障がいのある方が障がい者枠で就職することは、雇用する企業から配慮を示してもらいやすくなります。
例えば、勤務形態、業務内容について、何らかの難しさがあれば、勤務時間を調整したり、休憩を取りやすくする、障がい特性に応じたコミュニケーションツールの活用や、業務手順を変更するなどの配慮を示してもらえるかもしれません。また、就労支援機関が関わっているのであれば、定着支援や、直接企業に伝えにくいことがあるときに、本人と企業との間に入って調整してもらうこともできます。
就職後に何か課題がでてきた場合でも、ジョブコーチと呼ばれる障がい者を支援する専門家にサポートしてもらうことができます。ジョブコーチは、障がい者だけでなく、企業側に対してもサポートします。例えば、障がい者とどのように関わったらよいのか、配慮を示すことができるのかなどのアドバイスをおこなったりします。障がい者枠で就職すると、このようなサポートを受けやすくなるので、結果的に、職場に定着しやすくなります。
一方、職場の人が、障がい者を雇用していることを知らない場合には、職場でのコミュニケーションや業務の進め方を配慮することはほとんどありませんし、何か支障があったときにも周りの社員から理解を得にくく、人間関係が悪化してしまうこともあります。
障がい者雇用は一般雇用に比べ、求人の数が少ない傾向にあります。志望する企業が障がい者雇用の求人を出していないタイミングだったり、そもそも企業規模が小さくて障がい者雇用を実施していなかったりする場合もあります。
また、企業は障がい者の特性に合わせて業務の選定を行います。そのため業務内容が限定的になってしまう傾向があり、限定的であることで給与があまり上がらない場合もあります。人によってはやりがいを感じにくい可能性もあるでしょう。
障がい者雇用枠でチャレンジしたいと考えている方は、面接の際などに、企業側と雇用条件や業務範囲のすり合わせをすることをおすすめします。
厚生労働省が令和7年12月19日に発表した、令和7年6月1日現在の障がい者雇用状況の集計結果を見てみましょう。
障害者雇用促進法では、40人以上規模の企業には法定雇用率2.5%に相当する数の障がい者を雇用することが求められています。集計によれば、上記に該当する企業に雇用されている障がい者の数は70万4,610.0人。これは22年連続で過去最高の人数となっています。法定雇用率の段階的な引き上げとともに、企業の障がい者雇用は着実に広がりを見せている状況にあることがわかります。
また、雇用されている障がい者のうち、身体障がい者は37万3,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障がい者は16万2,153.5人(同2.8%増)、精神障がい者は16万8,542.0人(同11.8%増)という結果となりました。精神障がい者の伸び率が大きく、知的障がい者も伸びているのに対し、身体障がい者の雇用者数の伸び率は低いことがわかります。
※重度身体障がい者、重度知的障がい者は1人を2人としてカウント。
※短時間身体障がい者、知的障がい者は1人を0.5人、重度の場合は1人としてカウント。
※短時間精神障がい者は1人としてカウント(特例措置あり)
なお2024年4月1日より、週20時間未満の雇用の場合でも雇用算定対象となる、特例措置が始まっています。労働時間は10時間以上20時間未満である精神障がい者、重度の身体障がい者、重度の知的障がい者を雇用した場合、1人につき0.5カウントと算定されます。
企業規模別にみると、すべての企業規模において雇用障がい者数は増加していますが、実雇用率は、1,000人以上規模の企業を除くすべての規模で前年より低下しました。法定雇用率達成企業の割合も、100〜500人未満規模の企業で前年より低下しています。
令和7年に報告された法定雇用率未達成企業は6万5,033社。そのうち57.3%の企業が障がい者を1人も雇用していないという結果になりました。
今まで障がい者を雇用したことのない企業や雇用率が低いままの企業が、急に障がい者雇用率を上げようとしても、うまくいかない可能性があります。では、企業が障がい者雇用を促進するためにはどのようなことに取り組めばよいのでしょうか。そのポイントを3つご紹介します。
障がい者と関わったことがなかったり、障がい者を通じたトラブルを経験したりしている人は、障がい者雇用に対してあまり良いイメージを持っていない場合があります。
すべての社員に障がい者雇用について理解してもらうことは、すぐに達成できることではないでしょう。しかし、障がい者雇用に対する社内の理解を根気強く求めることが必要です。社内研修を通し、障がい者を雇用することの職場環境へのメリット、業務へのコミット例などを学び、障がい者雇用に対するイメージを良くする取り組みを行いましょう。
同時に、障がいにはさまざまな種類があり、同じ診断名が付いていても特性は人それぞれであること、雇用に際しては周りの人が環境や仕事内容を柔軟に調整する必要があることを伝えます。
その上で、障がい者も会社の戦力の1人として活躍していけるということを会社全体の認識として共有することを目指します。
管理職だけでなく全社員が障がい者雇用についての理解を深め、偏見のない正しい知識を得れば、雇用が促進されるだけでなく、雇用後の業務もスムーズに進みやすくなります。
障がい者が実際に働く現場では、その人がどのような特性をもっているのか、どこにサポートが必要なのかを共有し、その人に合ったサポート体制を整える必要があります。
実際に障がい者が雇用されたときにはもちろんですが、まだ障がい者がいない職場であっても、お互いの情報を共有し、それぞれにどのようなサポートがあると働きやすいのか、フォローしあえるところはどこかを意識して業務にあたることで、実際に障がい者と働く際にもスムーズに適応することができます。
「障がい者雇用の経験がなく、どう始めればいいのかわからない」「障がい者を雇用したことがあるが長く続いたことがない」など、障がい者雇用について課題をもっている企業の方には、障がい者雇用を総合的に支援するサービスの活用がおすすめです。
サービスを活用すると、障がい者雇用に取り組む前の業務の切り出しや社内理解の醸成からサポートしてもらえます。もちろん、障がい者の紹介から実際の雇用、さらには雇用継続まで、一貫した支援を受けられます。
注意点としては、サービスを提供する事業者へ任せきりになってしまうと、雇用ノウハウの蓄積や、前述したメリットが生まれません。サービスを利用する場合でも、主体的に障がい者雇用に関わることが大切です。
エスプールプラスでは、求人募集から雇用継続まで、企業の障がい者雇用を手厚くサポートしています。15年以上の実績のもと、初めての雇用でも安心してご利用いただけます。
また、地域の福祉機関や行政機関と連携して働きたい障がいのある方を募り、説明会・体験会を随時行っています。紹介から雇用後の定着支援まで伴走するため、自社のノウハウ蓄積にもつながります。
エスプールプラスの障がい者雇用支援サービスは、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの貢献にもつながる取り組みとして、多くの企業様にご利用いただいています。
こうしたサービスを活用すれば、障がいのある方が生き生きと働けるだけでなく、障がい者雇用に対する社内の理解も次第に深まっていくでしょう。障がい者雇用についてお悩みをお持ちの際は、お気軽にエスプールプラスにご相談ください。
障がい者雇用をすることの最大のメリットは法律で求められている障害者雇用率を達成できることですが、その他にも、業務を見直すきっかけをつくることや、社会的責任を果たすこと、多様性のある会社づくりができること、助成金を受け取れることなどもメリットとして挙げられます。
一方、障害者雇用率が達成できないと一定のペナルティがありますし、大幅な未達成がある場合は行政指導が入り、障害者雇用雇入計画書を出すことになります。それでも達成できないときには企業名が公表されることになります。



世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用...