

株式会社エスプールプラス
株式会社エスプールプラス 事業推進グループ 企業在籍型ジョブコーチ / 障害者職業生活相談員 植木 展子
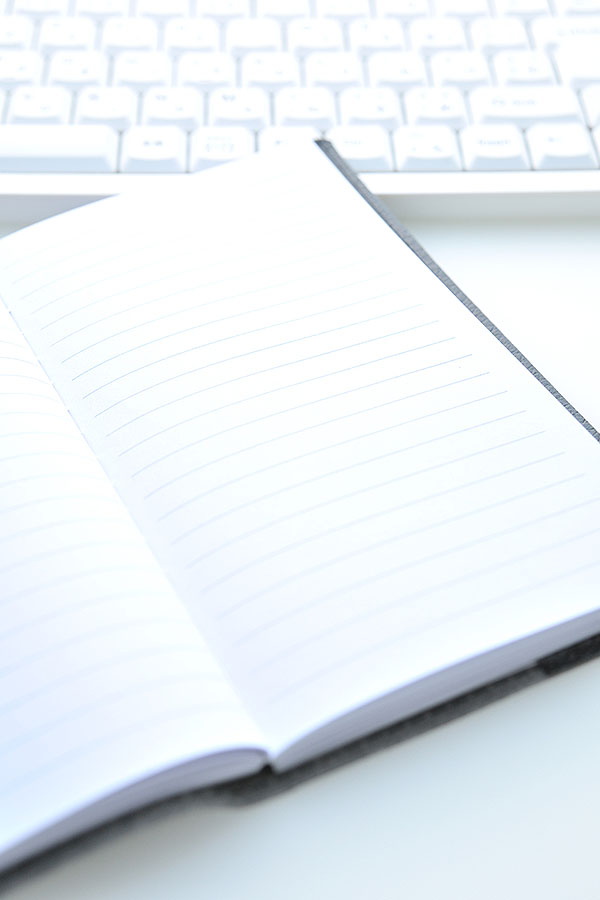
近年、ダイバーシティ&インクルージョンや人的資本経営への関心の高まりから、障がい者雇用を意欲的に推進する企業が増加傾向にある。一方で、法定雇用率の達成ばかりが目的となってしまっているケースも少なくない。障がい者雇用を単なる義務ではなく、企業成長の力とするためには何が必要なのか。株式会社エスプールプラスの植木氏が、障がいのある方と健常者の双方が尊重し合える文化醸成の重要性、社内にプラスの影響をもたらす障がい者雇用を推進するための具体的な3ステップを解説した。
株式会社エスプールプラスは、「一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する」という企業理念のもと、企業の障がい者雇用を支援する企業である。親会社である株式会社エスプールの100%出資子会社として、プライム市場上場企業のガバナンス体制に基づき、法令を遵守した事業を展開している。
同社のサービスは、15年前に独自開発した「わーくはぴねす農園」。障がいのある方々が安心安全に働ける場所を提供するため、野菜作りを通じた障がい者雇用を支援する「農園型」のサービスモデルである。創業当時、最低賃金を得て働くことができた障がいのある方は20人に1人という状況下で、就労を望んでも特性に合う環境がないという課題の解決を目指して事業を開始した。
農園型障がい者雇用支援サービスには、雇用主が農園を所有するタイプと、同社のように運営事業者が農園の貸し出しや人材紹介、定着支援までをワンストップで提供するタイプがある。同社はこの後者のモデルのパイオニアであり、全国58ヵ所の農園で700社以上の企業を支援し、4,700名以上の障がい者雇用を創出している。
法定雇用率の遵守という義務的な側面で語られがちだった障がい者雇用は、今や企業の競争力を高める戦略的な手段として注目されている。植木氏は、同社が実施したアンケート結果をもとに、多くの企業が障がい者雇用にポジティブな価値を見出している現状を明らかにした。
「調査では、回答企業150社のうち70.8%が『障がい者雇用の推進が企業価値向上につながる』と回答しています。さらに、実際に良い影響を得られたと答えた企業は95.7%に上り、その約6割が『社員の多様性への理解が深まった』と感じています」
では、障がい者雇用を意欲的に推進し、実際に企業価値向上につなげている企業にはどのような特徴があるのだろうか。植木氏は、成功している企業に共通する四つのポイントを挙げた。
こうした取り組みは、職場の心理的安全性向上にも直結する。ここで植木氏は、横浜市立大学の影山氏による研究成果を紹介した。
「研究では、職場に障がいのある方との接点が増えることで、従業員の倫理的な意識が刺激され、互いの違いを認識し、配慮し合う文化が育まれるプロセスが示されています。この相互尊重の積み重ねが心理的安全性の高い組織を育み、結果として組織全体の業務パフォーマンスを向上させるのです」
植木氏は、心理的安全性が担保された組織は、些細なエラー報告が活発になる一方で、経営に影響を及ぼすような重大インシデントは減少するという米国の病院での研究事例も挙げ、その重要性を強調した。

一方で、多様性を受け入れ合う文化が未醸成のまま、雇用率達成のみを目的として障がい者雇用を進めてしまうと、さまざまな問題が生じる。植木氏は、こうした「ネガティブな推進」が、障がいのある方と健常者の双方に及ぼす悪影響について警鐘を鳴らす。
「一方で、健常者の側にも悪影響は及びます。障がいのある方への偏見が残る職場では、彼らと共に働くことでの業務負担への懸念が生まれやすいからです。また、接し方が分からないためコミュニケーションについて不安を感じたり、職場環境の変化そのものに抵抗感を抱いたりすることもあります。さらに、心理的安全性が低い組織では、障がい者雇用がうまくいかなかった場合の社内評価への影響を恐れ、担当者が過度なストレスを抱えることにもなりかねません」
こうした状況が続けば、双方に不満やストレスが蓄積し、チームワークの乱れやエンゲージメントの低下を招き、最終的には組織崩壊につながる可能性すらあるという。
「だからこそ大切なのは、多様性を受け入れ合う文化を職場の土台として育てること。その上で障がい者雇用を、企業価値を高めるための戦略として社内に広めていくことが必要です。こうした意識が広がっていけば、障がいのある方も健常者も安心して力を発揮できる、本当の意味での障がい者雇用の推進が実現できると考えています」
では、具体的にどのようにすれば、相互理解に基づいた意義ある障がい者雇用を実現できるのか。植木氏は、そのための具体的なロードマップである「3ステップ」を提示した。
最初のステップは、障がいのある社員が安心して働ける環境を整備することである。バリアフリー設計やサポート体制の充実はもちろんのこと、多様な人材が活躍できるよう幅広い職種を用意するなど、人が会社に合わせるのではなく、会社が人に合わせる環境を整えることが重要だ。本社内での整備が難しい場合は、農園やサテライトオフィスといった外部の選択肢を活用することも有効な手段となる。この導入の段階で得られる安心感や成功体験が、次への基盤となる。
環境が整ったら、次は障がいのある社員と健常者社員の接点を段階的に増やしていく。植木氏が特に重要だと強調するのは、健常者が障がいのある方に教わるという体験だ。障がいのある社員が誇りとやりがいをもって活躍している現場に健常者が関わり、仕事を教わったり、その質の高い成果物に触れたりする体験を通じて、健常者側が抱いていた偏見が自然と解消され、相互理解が深まっていく。
相互理解と尊重の文化が根付いてきた段階で、障がいのある社員が携わる業務領域を拡大する。ポイントは、社内で本当に必要とされている業務と、本人の特性や強みを的確にマッチングさせることだ。近年はデザイナーやエンジニア、企画アシスタントといった職種に加え、SNS運用や動画編集など、よりクリエイティブで戦略的な業務で活躍する事例も増えている。活躍の場を広げることが、企業全体の成長に貢献していく。
「私も、自社でこの3ステップを実践してきました。特に重視しているのが『採用方針の徹底』と『活躍の見える化』です。採用では、データ分析やデザイン制作といった社内の具体的なニーズに基づき、それにマッチする人材を獲得。既存業務を見直し、柔軟に形を変えることで、多様な人材が活躍できる土壌を作ってきました。
また、活躍の見える化として、ジョブコーチや障がい者雇用に理解のある社員をサポート役として間に配置することで障がいのある方の活躍が周囲にも自然と伝わるような座席の工夫や、それぞれの得意・不得意をまとめた「スキルマップ」の全社共有といった取り組みを紹介。スキルマップは、植木氏のアイデアを基に障がいのある社員が主体的に作成したものであり、こうしたプロセス自体が本人の能力を引き出すことにつながっているという。
これらの積み重ねの結果、同社では2025年3月末時点で4.74%という高い障がい者雇用率を維持している。段階的なアプローチで相互理解の土台を築くことが、最終的に企業価値向上という大きな果実につながるのである。

講演の後半では質疑応答の時間が設けられた。
植木:スキル要件はあくまで目安とし、柔軟な姿勢で臨むことが重要です。採用前後の面談や実習を通して、候補者のできることや得意なことを丁寧にすり合わせるのが効果的です。障がいのある方の場合、環境や配慮次第で能力を発揮できるケースも多いため、採用時点では伸びしろや学習意欲も評価に加えることが現実的だと考えます。
植木:初期段階では「障がいのある方=配慮が必要な人」というイメージだけで終わらせない工夫が必要です。具体的には、社内報や定例会議などで「この仕事でこんな活躍をしている」といった戦力としての側面を積極的に発信することが有効です。得意なことや工夫していることにスポットライトを当てることで、周囲の理解が自然と進みます。
植木:新しい業務を任せる際は、段階的に成功体験を積ませることを最優先に考えてください。まずは一つの業務に集中できる設計にし、「できたね」「助かったよ」といった丁寧なフィードバックで小さな成功体験を積み重ねてもらうことが大切です。また、業務の目的や相談先を事前に明確にしておくことで心理的負担を軽減でき、本人の自己効力感や成長意欲につながっていきます。
今日の講演をきっかけに、障がい者雇用が皆さまの企業の成長へとつながれば幸いです。本日はありがとうございました。
| 会社名 | 株式会社エスプールプラス |
|---|---|
| 事業内容 | 株式会社エスプールプラスは、「一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する」を企業理念とする障がい者雇用支援企業。独自開発した「わーくはぴねす農園」による農園型障がい者雇用支援サービスを提供。全国58ヵ所の農園で700社以上の企業を支援し、4,700名以上の障がい者雇用を創出。農園の貸し出し、人材紹介、定着支援までをワンストップで提供するサービスモデルのパイオニアとして事業を展開している。 |

