
障がい者手帳をもった方に限定した雇用枠である障がい者雇用枠。事業主は助成金などの支援を受けやすく、働く障がい者も、障がい者手帳を持っていることをオープンにしつつ特性や能力を活かした働き方がしやすい傾向にあります。
ここでは、障がい者雇用枠での採用のメリットや一般雇用枠との違いを解説します。
障がい者雇用枠とは、事業主が障がい者に限定して採用する雇用枠です。障がいのある方でも働きやすい雇用形態であり、障がいに対する配慮を受けながら仕事を続けやすい傾向にあります。ただし、障がい者雇用枠にエントリーできる条件など、一般雇用枠との違いもあるため、企業としてもその特徴を正しく理解しておくことが重要です。
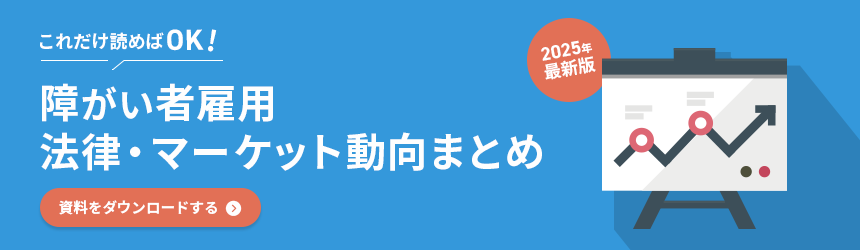
障がい者雇用枠の求人にエントリーできるのは、障がい者だけです。この場合の障がい者とは、以下のいずれかの手帳を所持している方を指します。
どの手帳であっても、それを保持していることで障がい者雇用の求人にエントリーできます。
参照:厚生労働省|事業主の方へ
障がい者雇用において、障がい者雇用枠と一般雇用枠の大きな違いは、障がいがあることを前提としているかどうかという点にあります。
それを念頭に置いて、それぞれの違いを比較してみましょう。
| 障がい者雇用 | 一般雇用 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 障がい者手帳を持つ障がい者に限る | すべての人が対象 |
| 業務内容 | 障がい特性に応じた業務 | 一般的な業務がベース |
| サポート体制 | 障がいを前提とした合理的配慮が受けられる | 障がいへの配慮は受けづらい |
| 雇用の安定性(※) | 1年後定着率70.6% | 1年後定着率49.9%(障がいを開示した場合)・30.8%(非開示の場合) |
事業主の義務としての障がい者雇用を定めた法律として、障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)があります。国はこの法律の目的について、「障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ること」と定めています。そのために、事業主に対してさまざまな義務を定めると同時に、助成金を用意しています。
障害者雇用促進法によって定められている事業主の義務の1つが、法定雇用率制度です。これは、常用労働者数に応じて一定割合の障がい者を雇用することを義務づけた制度です。
令和7年4月現在の民間企業における法定雇用率は2.5%(国・地方公共団体は2.8%、都道府県等の教育委員会は2.7%)で、常用労働者数が40.0人以上のすべての事業主が障がい者雇用義務の対象となっています。法定雇用率は段階的に引き上げられ、令和8年7月には2.7%(国・地方公共団体は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%)になることが決まっています。事業主は、毎年6月1日時点での障がい者雇用の状況を報告する義務があり、未達成の事業主には行政指導が入る場合があります。
これらの背景により、障がい者雇用に対する事業主の意識は時代とともに高まっています。実際、障がい者雇用枠の求人数は令和2年度の19万4,741人から右肩上がりで、令和5年度には26万3,217人に達しており、障がい者雇用に取り組む事業主が増えていることがわかります。

障がい者雇用は事業主に課せられた社会的義務の1つです。「義務だからやむを得ない」というスタンスで取り組んでいる担当者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、障がい者雇用を積極的に取り組むことには、法定雇用率の達成だけではないメリットがあります。
代表的なメリットは以下の3点です。
それぞれ詳しく解説します。
近年、ダイバーシティの取り組みへの関心度が高まり続けています。障がい者雇用を推進して法定雇用率を達成し、障がいのある方が活躍する会社にしていくことは、企業の社会的信頼や評価の向上につながります。
障がい者雇用を実施していると、さまざまな助成金や税制優遇措置が受けられます。
助成金には以下のようなものがあります。
助成金の詳しい条件や支給額については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、障がい者を雇用している事業所向けの税制優遇措置には以下の2つが挙げられます。
社内で障がいのある方が活躍することは、さまざまな立場や価値観を尊重し合う多様性のある組織づくりにつながります。多様性が促進されることで、社員同士が互いを理解し合い、心理的安全性の高い職場環境が築かれることが期待できます。
さらに、こういった職場環境は、障がいの有無に関わらず幅広い人材を受け入れる土台となり、人材確保をしやすくなるといったメリットも生み出します。
事業主が障がい者雇用枠を設けることにはさまざまなメリットがある反面、いくつかのデメリットも存在します。
よくあるデメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
障がい者雇用を取り組みはじめる際には、社内の業務から障がい者に割り当てられる業務を切り出し、特性に合わせて能力を発揮できるようにしなければなりません。また、時短勤務やリモート勤務を取り入れるなど、雇用管理も見直しが必要になる場合もあります。
雇用後の教育やサポート体制を整えることも欠かせません。障がい者が安心して働き続けられるように、障がい者雇用のための担当者を配置し、いつでも相談しやすい環境をつくることが重要です。担当者には、障がい者本人と一般社員の間に立ち、合理的配慮の提供と周囲の理解を広めることが求められますが、そのための人員を割く人的コストがどうしてもかかります。必要に応じてジョブコーチや支援員を招くこともありますが、そのコストが負担になることもあるでしょう。
このように、障がい者雇用に取り組む際には手間とコストが発生するため、デメリットと感じられる場合があります。だからこそ、数合わせの雇用ではなく、前述のメリットを享受しながら、他の従業員にとっても働きやすい職場環境をつくっていくことが大切です。
障がい者雇用枠で働くことは、障がいのある方にも大きなメリットがあります。ここでは、代表的な2つをご紹介します。
障がい者雇用枠は、従業員が障がい者であることを前提とした働き方です。事業主も受け入れる準備を整えたうえで雇用するため求職者は自分の特性や得意なこと、必要な合理的配慮をオープンにして働くことができます。
そのため、障がい特性上難しい業務を充てられることは少なく、合理的配慮を受けながら得意を活かして職務にあたることが可能です。
こうした理解や配慮は長く仕事を続けていくうえで必要不可欠なことです。特性をうまく活かしながら働き続けるためにも、障がい者雇用枠で採用されることのメリットは大きいでしょう。
障がいがあっても一般雇用枠での採用を目指すという選択肢はありますが、一般採用の場合、採用時に障がいの考慮は得にくくなります。 つまり、障がい者手帳を持っていない人と同じ立場で選考が進むため、障がい特性がハンデになってしまう可能性もあるのです。
一方、障がい者雇用枠の場合、エントリーできるのが障がい者に限られ、企業には法定雇用率に基づく雇用義務もあります。そのため、求人によっては倍率が低いものもあり、一般雇用枠を狙うよりも就職しやすくなっていることがあります。
障がい者雇用枠で働く条件や応募方法についてはこちらをご覧ください。
「障害者雇用で働くための条件について」
雇用する側と同じく、障がいのある方にとっても、障がい者雇用で働くデメリットはあります。代表的なものを2つご紹介します。
障がい者雇用では、企業側は障がい者の特性に配慮した業務を用意しているため、業務内容が限定されやすい傾向にあります。
長く働くことでスキルや能力が認められれば、業務内容が広がることもあります。
障がい者雇用枠は一般雇用枠に比べて配慮により業務内容や業務時間が限定されていることから、昇進の機会が限られる場合があります。キャリアアップを希望する方は、体調や特性を鑑みながら上長の方と適切にキャリアを積んでいくことが必要です。

最後に、企業が障がい者雇用枠で採用活動をする場合の大まかな流れをご紹介します。
障がい者を雇用するにあたっては、社内の理解を深めることが不可欠です。研修などを通して、障がい特性や合理的配慮の例などの理解を深めましょう。可能であれば、実際に障がい者が働いている職場や就労移行支援事業所などに見学にいくことも有効です。
社内の理解が深まったら、実際に障がい者を雇入れる準備をします。まずは、職場環境や職務内容などを踏まえ、障がい特性があっても働きやすい配置部署を決めましょう。その上で今ある業務を洗い出し、障がい者に割り当てる業務の切り出しをおこないます。備品の整理や業務のマニュアル整理なども併せておこないましょう。
割り当てる業務が決まったら、労働条件を決めます。勤務時間や給与など、業務内容に見合った形で決定しましょう。
労働条件まで決定したら、求人募集をかけます。募集先としては、ハローワークに加え、障がい者専用の求人サイトなどもあるので、積極的に活用しましょう。就労移行支援事業所や支援学校と連携する方法も効果的です。エントリーがきたら、書類選考や面接を実施し、採用します。
障がい者雇用は採用して終わりではありません。その先の職場定着までのサポートが必要です。
障がい特性は人それぞれです。特性を考慮して割り当てた業務が本人にとっては難しかったり、逆に簡単すぎてやりがいが得られなかったり、という可能性もあります。能力と職務のギャップが生じないよう、定期的に面談を実施しましょう。そのなかで、どのような配慮が必要なのかのヒアリングもおこない、本人の能力が発揮できる環境を整え、長期的に働けるようサポートします。

障がい者雇用枠は、障がい者に特化した雇用形態です。事業主にとっては、助成金や公的支援を活用しながら障がい者雇用を進めることができます。また、積極的な取り組みは、法定雇用率の達成のみならず、社会的信頼にもつながります。
障がい者にとっても、障がい者雇用枠は活用しやすい制度です。一般雇用に比べて周囲の理解や配慮を受けやすく、長く働ける可能性も高まります。
障がい者雇用枠という制度をうまく使うことは、障がいの有無に関わらず、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場環境を整えることにつながるのです。


世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用...