
ダイバーシティ経営という言葉を聞いたことはありますか? 多様な人材がともに働き、個々の能力を発揮できる環境を整えることで、企業の利潤を高める経営手法のことを指す言葉です。
実は、このダイバーシティ経営のカギを握るのが、障がい者雇用です。この記事では、ダイバーシティ経営と障がい者雇用の関係性、雇用の進め方などを解説します。
ダイバーシティとは、直訳すると多様性を意味します。年齢や性別、宗教や人種などの属性に関わらず、多様なバックグラウンドをもつ人々が共存している状態です。つまり、ダイバーシティ経営とは、多様な人材がともに働き、個々の能力を発揮できる環境を整えることで、企業全体の利益の向上、組織全体の競争力強化を目指す経営手法を意味しています。
ダイバーシティ経営が注目される背景にはいくつかの社会的要因があります。
一つ目は、市場のグローバル化です。いま、あらゆる市場でグローバル化がすすみ、市場環境の変化もスピードを増しています。国外の企業との競争も激しくなりました。刻一刻とうつりかわるこの状況には、画一的な人材を確保するだけでは太刀打ちできません。あらゆる価値観や能力を有した人材がそれぞれの分野で活躍できるような環境を整えていく必要があるのです。
二つ目は、細分化された顧客ニーズへの対応の必要性です。SNSやインターネットの普及により、消費者の間にはさまざまな価値観が広がるようになりました。また、ライフスタイルによる消費行動の多様化もすすみ、集団ニーズの輪郭がぼやけています。
企業はいま、さまざまなニーズをもつ人々に広く求められる商品やサービスを開発しなければ生き延びていけません。また、さまざまな商品やサービスを開発するためには多様な人材を確保しなければなりません。
三つ目は、少子高齢化による人材不足の影響です。労働人口が減少していくなか、いかに人材を確保するかは企業の喫緊の課題です。年齢や性別、障がいや宗教などに関わらず、あらゆる人材が活躍できる環境を整えれば、人材の間口が広がり、人材不足の解消、ひいてはあたらしい企業利益の創出につながります。
以上のような要因からダイバーシティ経営は注目を集めており、その重要度は今後も増していくことが予想されます。
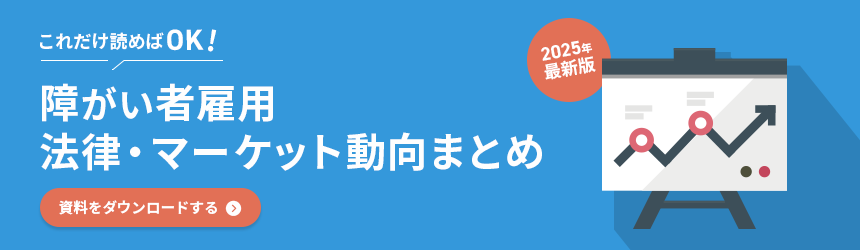
グローバル化やSNSの普及などにより、多様性の理解は社会に広まりつつあります。さまざまな国籍の人がともに働くオフィスも珍しくはなくなり、性的マイノリティを公開して生活する人も増えてきました。
しかし、障がいの有無は見過ごされやすい要素です。社会のなかに障がいのある方が一定数いることは認識されている一方、その存在が個々の生活や企業に密着しているかといえば、決してそうとはいえないでしょう。
障がい者雇用は企業の義務として法律で定められており、違反するとペナルティが課せられます。そのため、ペナルティを避けるために義務的に雇用に取り組んでいるという企業も少なくありません。義務の一歩先をすすみ、障がい者雇用と企業利益をつなげられている企業は、ほんのひとにぎりです。
本当のダイバーシティを実現するためには、障がいの有無に関わず、すべての人が共に働く職場をつくることが重要です。そこには、段差をなくす、机や椅子を工夫するといったハード面での環境づくりのほか、目に見えない困難を抱えている方に対する合理的配慮の提供や障がいの理解といった、社員のノーマライゼーション意識も関わってきます。
それらを包括して誰もが安心して活躍できる職場環境をつくることが、真のダイバーシティを実現する第一歩となります。

障がい者雇用は企業の義務として定められており、多くの企業が法定雇用率を達成するためにさまざまな対応をしています。
しかし、厚生労働省が公開している令和6年の障害者雇用状況の集計結果によると、民間企業の法定雇用率達成割合は46.0%。半数以上の企業が法定雇用率未達成という状況です。法定雇用率が徐々に引き上げられているなか、障がい者雇用に苦心している企業が多いことがうかがえます。障がい者雇用の取り組みが不足している場合はペナルティとして厚生労働省のホームページで企業名が公表されますが、令和5年度には1社が企業名公表のペナルティを受けています。
企業のなかには、障がい者雇用を法定雇用率を満たすことだけが目的となってしまっているケースもあります。その背景には、通常業務に追われる中、障がい者雇用に時間やスタッフをさくことができない、障がい者雇用のノウハウがないなど、企業ごとにいろいろな理由があるでしょう。しかし、定着や活躍に向けた設計がないまま雇用することで、業務の切り出しができなかったり、雇用しても定着しなかったり、社内の理解が得られなければ[星田3.1][杉井3.2]、現場は疲弊してしまい、障がい者雇用はさらに進みにくくなります。
企業が持続して利益を上げていくためには、障がい者雇用への取り組みを強化し、本当の意味で多様性のある環境を創出することが必須です。
障がい者雇用を進めることは、企業のダイバーシティ経営を推進するうえで非常に重要になります。
障がいとひと口にいっても、その種類や程度、特性や求められる配慮などは人それぞれです。雇用の際、「この種類でこの程度の障がいのある方」と限定してしまうと、いつまでたっても障がい者雇用は進みません。大切なのは、一人ひとりにあわせた配慮をすることです。
そのために求められることは、社員同士の対話と理解です。対話を通してその方の障がい特性を理解し、どのような合理的配慮が必要なのかを知って、それを実践すること。その土壌が出来上がっていれば、さまざまな種類や程度の障がいのある方が活躍できる場となることでしょう。
そして、それはダイバーシティ経営の推進にも直結することです。人種、宗教、性別など、人がそれぞれに持つバックグラウンドや個性の違いを対話を通して理解し、認め合うこと。それによって多様な人材が活躍し、成長し続けられる企業になるのです。
障がい者雇用をより前向きに進めたい人事・採用担当者の方に向けて、「ダイバーシティ&インクルージョンの視点から考える障がい者雇用の価値」セミナーを開催しています。
セミナー詳細・申込ページはこちら >
障がい者雇用はダイバーシティ視点でも欠かせない要素であることを解説しました。ここからは、障がい者雇用を具体的にどのように進めればいいのかを解説します。
前提として、障がいのある方は障がい特性や求められる合理的配慮がそれぞれに異なることを理解しましょう。そのうえで、雇用する社員はどのような特性や個性があり、どのような業務が得意なのか、逆に難しい業務や配慮が必要な事柄はなにかを丁寧にヒアリングします。本人の希望や要望を理解したうえで、それに合わせた職域や働き方を設計します。
業務の切り出しや雇用条件などが障がい者を雇用する前段階で決まっていることも多いでしょう。それをベースに考えつつ、しかし、それにとらわれることなく、本人の特性や成長に合わせて柔軟に仕事を割り振ることが、雇用継続に繋がるカギとなります。
働き方についても同様です。無理な勤務時間や日数で働き始めると、体調を崩して長続きしながったり、仕事のポテンシャルが下がってしまったりすることが考えられます。勤務時間を短くする、必要に応じてリモートワークを取り入れるなど、さまざまな選択肢の用意を検討しましょう。
障がいのある方が安心して働くためには、心理的な安全性や合理的配慮を整備することも重要となります。
合理的配慮とは、人がその人らしく働くために求められる配慮のことで、企業にはそれを提供する義務があります。具体的には、オフィス内の段差をなくす、机や椅子を調整可能なものにするといった物理的な配慮のほか、オフィスの掲示物や壁紙の色、防音設備などについて配慮が必要な場合もあります。どのような配慮が必要かは人それぞれであるため、ここでも対話が重要です。
障がい者雇用は雇用担当者だけが取り組んでいてもうまくいきません。周囲のサポート体制を整えるためにも、社内の意識改革が重要となります。
社内には、障がい者雇用への取り組みを負担に感じている社員や目的がわからない社員もいるかもしれません。法定雇用率を達成しなくてはいけないからという理由以上に、会社のダイバーシティ経営において有意義な取り組みであること、会社にとってメリットが大きい取り組みであることを理解できるよう、研修などをおこないましょう。あらゆる立場の社員が活躍できる環境を会社全体でつくるという目的を全社員で共有すれば、多様性を尊重する土壌が育ち始めます。


企業が持続し成長していくために、ダンバーシティという経営観点は非常に重要な立ち位置を占めるようになりました。そして、ダイバーシティ経営においては障がい者雇用が欠かせない大切な取り組みとなってきました。
また、障がい者雇用を推進するためには、社内の理解を深めたり、オフィス環境を整えたりといった対応が必要です。それらの対応は、そのまま多様性を受け入れる環境づくりに直結します。
エスプールプラスでは、企業と二人三脚ですすめる障がい者雇用支援サービスを提供しています。専門スタッフが企業の課題をしっかりサポートし、雇用継続まで一貫して支援します。ご興味をお持ちの際はぜひお気軽にお問い合わせください。


世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用...