
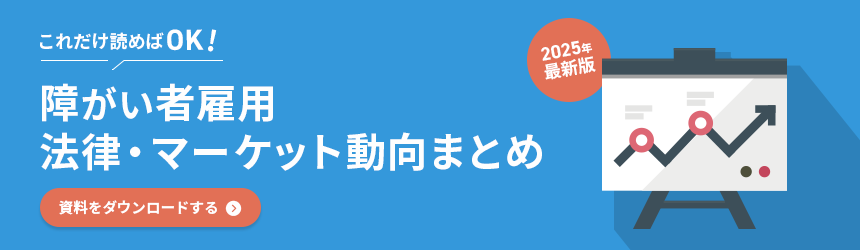
障がいのある方の雇用の創出と自立の促進は、現代社会において大切な課題のひとつです。
障害者雇用促進法により、各事業主に障がい者の法定雇用率の遵守が義務付けられていますが、事業主が広く障がい者の雇用を受け入れるためには、適切な職場環境の整備など、事前の準備が必要です。そして、その準備には決して少なくないコストがかかります。そのため、国や自治体では、障がい者の雇用を促進するための助成金や補助金を用意しています。
この記事では、障がい者を雇用する事業主に対して国から支給される各種の助成金・補助金について、その概要を解説します。
企業が障がい者を雇用する際に申請できる助成金・補助金には多くの種類があります。また支給にあたっては、条件、実雇用率についてなど、さまざまな決まりがあります。
障がい者を雇用する際には、職場のバリアフリー化など、障がい者が安全に働けるよう職場環境を整える必要があります。また、さまざまな特性の障がい者を受け入れるためのサポート体制を整えることも重要です。事業主がこれらの環境整備をし、障がい者をスムーズに雇用できるよう、国ではさまざまな助成金制度を用意しています。
また、国が実施している助成金制度のほかに、各自治体で補助金制度を導入している場合もあります。これは障がい者雇用を推進するために各自治体が独自におこなうもので、施設の整備に関するものや雇入れに関するものなどがあります。自治体によっては奨励金として支給している場合もあるため、確認してみましょう。
障がい者の雇用に関する助成制度は数多くあり、受給要件も細かく設定されています。では、障がい者雇用に関する助成金の受給対象となる事業主とは、どんな企業なのでしょうか。
厚生労働省では、各助成金に共通する要件について、下記の3点を提示しています。
また、地方自治体の補助金制度を利用するためには、その制度を導入している自治体に居住している障がい者を雇用する、その自治体に事業所がある、などの条件を満たす必要があります。

障がい者の雇用に関する助成金はどんなものがあるのでしょうか。ここでは、各種助成金の種類とその概要を網羅的に記載します。受給金額の目安についても参考にしてください。
障害者雇用に関する助成金は、障がい者の雇い入れや雇用の継続にあたって、事業主が措置を講じる際に支給されます。助成金の種類はさまざまで、障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金やトライアル雇用助成金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金などが該当します。
助成金の内容や支給要件などはさまざまですので、それぞれ確認してみてください。
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金は、障がい者の雇用に際して作業施設や福祉施設の設置を行う事業主に対して支給されます。保健施設、給食施設、教養文化施設などの福利厚生施設が該当します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 障害者作業施設設置等助成金 |
| 支給要件 | 障がい者を雇い入れる、または継続して雇用する事業主で、施設等の設置・整備をおこなわなければ障がい者の雇入れや雇用継続が困難と認められるもの |
| 支給額 | 設置等に要した費用の3分の2 |
| 対象障がい者 | 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者で、作業施設等の設置や整備をおこなわなければ雇入れや雇用の継続が困難と認められる方 (身体障がい者および知的障がい者の特定短時間労働者については、重度障がい者に限る) |
| 支給期間 | 3年間 |
| 注意点 | 申請前に着工や契約などをおこなってしまうと支給対象外 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 障害者福祉施設設置等助成金 |
| 支給要件 |
次の2つの要件に当てはまる事業主であること。
|
| 支給額 | 対象障がい者1人につき225万円(重度身体障がい者・重度知的障がい者・精神障がい者以外の短時間労働者または特定短時間労働者の場合は1人につき112.5万円)を限度とし、設置等に要した費用の3分の1を支給。 ただし、同一事業主の団体につき一年度あたり2,250万円を限度とする |
| 対象障がい者 | 申請日の時点で雇用されている身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 |
| 支給時期 | 認定日から起算して1年以内に福祉施設等の設置・整備および経費の支払いを完了させた状態で支給請求書を提出し、受理後に支給 |
| 注意点 | 申請前に着工や契約などをおこなってしまうと支給対象外 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
障害者介助等助成金は、障がい者を雇用するにあたり必要な介助者を職場に配置ないしは委嘱する事業主に対して支給されます。職場復帰支援助成金、中途障害者等技能習得支援助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金など、20の項目で助成金が設けられています。支給額や支給要件はそれぞれ異なります。
重度障害者等通勤対策助成金は、通勤が特に困難であると認められる重度の障がい者に対し、事業主が通勤対策をおこなう際に支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 重度障害者等通勤対策助成金 |
| 支給要件 | 対象障がい者を雇用し、通勤について必要な措置をおこなわなければ雇用の継続が困難と認められる事業主、またはその事業主の加入する事業主団体 |
| 支給額 | 実施する通勤対策によって異なる |
| 対象障がい者 | 重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・通勤が特に困難と認められる身体障がい者 |
| 支給時期 | 実施する通勤対策によって異なる |
| 注意点 | 申請前からおこなっている措置は助成金支給の対象外 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
具体的には、以下の8種類の助成金が設けられています。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度の障がい者を継続的に多数雇用している事業主が、これらの障がい者のために事業施設の設置や整備を行う際に利用できる助成金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
| 支給要件 |
対象障がい者を多数雇用し、今後も安定した雇用継続が認められる事業主で、以下の2つの要件に該当し、支給対象事業施設の設置や整備をおこなうこと
|
| 支給額 | 5,000万円を限度額とし、支給対象費用(※)の3分の2を支給(特例の場合は1億円を上限とし、支給対象費用の4分の3を支給) |
| 対象障がい者 | 重度身体障がい者(特定短時間労働者を除く)・知的障がい者(重度知的ではない短時間労働者および特定短時間労働者を除く)・精神障がい者(特定短時間労働者を除く) |
| 支給時期 | 認定日から起算して1年以内に福祉施設等の設置・整備および経費の支払いを完了させた状態で支給請求書を提出し、受理後に支給 |
| 注意点 | 申請前に着工や契約などをおこなってしまうと支給対象外になる |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
※支給対象費用=支給対象面積×対象施設の1平方メートルあたりの建築等単価
障害者職場実習支援事業は、障がい者を雇用したことのない事業主がハローワークなどと協力して職場実習を実施した際に支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 障害者職場実習支援事業(障害者職場実習等受入謝金/実習指導員への謝金) |
| 支給要件 |
以下の項目に該当する事業主 【すべてに該当】
|
| 支給額 |
|
| 対象障がい者 |
ハローワークに求職登録している方、障がい者職業センター等で支援を受けている方、就労支援事業所の利用者、特別支援学校の生徒のうち、次のいずれかに該当する方
|
| 支給時期 | 職場実習等の措置が終了した日(あるいは認定通知日)が属する月の翌々月末までに請求書を提出し、審査を経て支給 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
トライアル雇用助成金は、障がい者を原則3ヵ月間試行雇用するトライアル雇用を実施する企業に支給されます。トライアル雇用は、障がい者の雇用機会を増やす試みとして設置されました。この助成金には、障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。
障害者トライアルコースは、一週間の所定労働時間が正規雇用の従業員と同程度の30時間以上と設定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 障害者トライアルコース |
| 支給要件 | ハローワーク等の紹介により対象障がい者を雇入れ、トライアル雇用等の期間について雇用保険被保険者資格取得の届出をおこなうこと |
| 支給額 | 対象の労働者が精神障がい者の場合は、最初の3ヵ月間は月額最大8万円、次の3ヵ月間は月額最大4万円を支給。それ以外の障がい者の場合は、月額最大4万円を支給 |
| 対象障がい者 |
継続雇用を希望したうえで障害者トライアル雇用についても希望している障がい者のうち、以下のいずれかに該当する者
|
| 支給期間 | 対象労働者が精神障がい者の場合は6ヵ月間、それ以外の障がい者の場合は3ヵ月間 |
| 注意点 | ハローワークのトライアル希望求人での雇用においての助成であるため、雇用後にトライアルコースに変えることはできない |
| 申請手続先 | 管轄のハローワークまたは労働局 |
障害者短時間トライアルコースは、最初は週10時間以上20時間未満の勤務から開始し、勤務者の状況に合わせて最終的に週20時間以上の勤務に引き上げることを目標にしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 障害者短時間トライアルコース |
| 支給要件 | ハローワーク等の紹介により対象障がい者を雇入れ、3ヵ月から12ヵ月間の短時間トライアル雇用をすること |
| 支給額 | 支給対象者1人につき最大4万円/月(最長12ヵ月間) |
| 対象障がい者 | 継続雇用を希望したうえで障害者トライアル雇用についても希望している精神障がい者または発達障がい者 |
| 支給期間 | 最長12ヵ月間 |
| 注意点 | ハローワークのトライアル希望求人での雇用においての助成であるため、雇用後にトライアルコースに変えることはできない |
| 申請手続先 | 管轄のハローワークまたは労働局 |

特定求職者雇用開発助成金は、特定の条件を満たした求職者を新たに雇用した企業に支給される助成金です。障がい者の雇用に関するコースとしては以下の3つがあります。
※特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)は、令和3年3月31日をもって廃止されました。
特定就職困難者コースは、障がい者や高齢者などの就職困難者をハローワークなどを介して雇用する事業主に対して支給される助成金です。本コースの助成金を受給するには、対象の労働者を継続的に雇用することが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 特定就職困難者コース |
| 支給要件 | 対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業所などの紹介により雇入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実だと認められること |
| 支給額 |
雇用されるのが重度障がい者等を除く身体・知的障がい者の場合は、年額120万円(50万円)を2年間(1年間)、重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者及び精神障がい者は年額240万円(100万円)を3年間(1年6ヵ月)支給。 短時間労働者の場合は障がいが重度であるかの区別はなく、年額80万円(30万円)を2年間(1年間)支給。 ※カッコ内は中小企業以外の事業主についての内容 |
| 対象障がい者 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 |
| 支給期間 | 雇用されるのが重度障がい者等を除く身体・知的障がい者の場合は2年間(1年間)、重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者及び精神障がい者は3年間(1年6ヵ月)支給 短時間労働者の場合は障がいが重度であるかの区別はなく、2年間(1年間)支給 |
| 申請手続先 | 管轄のハローワークまたは労働局 |
この助成金は、雇入れ後の申請や直接募集、求人サイトでの雇入れは助成の対象となりません。また、雇用関係のもと職場実習などがおこなわれた場合や雇用関係のない職場実習などが通算して3ヵ月を超える場合も助成の対象からはずれるため、注意が必要です。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)
発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースは、発達障がい者または難治性疾患患者を継続雇用する事業主に対する助成金です。事業主には雇用した労働者に対する配慮事項を報告する義務が課され、雇用から約半年後にハローワーク職員による職場訪問を受けることになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース |
| 支給要件 | 対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業所などの紹介により雇用保険一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実だと認められること |
| 支給額 |
中小企業の場合:短時間労働者1人あたり80万円/年、それ以外の労働者は120万円/年を支給(2年間)。 中小企業でない場合:短時間労働者1人あたり30万円/年、それ以外の労働者は50万円/年を支給(1年間)。 |
| 対象障がい者 | 発達障がい者・難病患者 |
| 申請手続先 | 管轄のハローワークまたは労働局 |
障害者初回雇用コースは、これまで障がい者雇用の経験がない中小企業が初めて障がい者を雇用した際に申請できる助成金です。この助成金はすでに廃止されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 障害者初回雇用コース(廃止) |
| 支給要件 | 過去3年間に対象障がい者の雇用実績がなく、初めて対象障がい者を雇入れ、最初の対象障がい者を雇入れた翌日から3ヵ月間に法定雇用率を達成する中小企業(常時労働者数43.5~300人)の事業主であること。 |
| 支給額 | 120万円 |
| 対象障がい者 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 |
障害者雇用安定助成金は、以前は障害者職場適応援助コース、中小企業障害者多数雇用施設設置等コース、障害者職場定着支援コースの3つのコースがありました。しかし、令和3年度より助成金の整理・統廃合が行われ、大幅に変更されています。
キャリアアップ助成金とは、障害の有無に関係なく、非正規雇用者のキャリアアップのため正社員化などを実施した事業主に対して助成金を支給するものです。そのうち障害者正社員化コースが、令和2年度まであった障害者雇用安定助成金の正規・無期転換の分野を引き継いだものとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) |
| 支給要件 |
対象障がい者等を雇用している事業主が、以下のいずれかの措置を継続的に講ずること
|
| 支給額 |
【重度身体・知的障がい者および精神障がい者】
|
| 対象障がい者 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・発達障がい者・難病患者・高次脳機能障がいと診断された者 |
| 支給期間 | 1年間(最初の6ヵ月を第1期、次の6ヵ月を第2期とし、支給額の半分の額ずつが支給される) |
| 注意点 | 実施前にキャリアアップ計画書を提出する必要がある。前に実施した措置は支給対象外 |
| 申請手続先 | 管轄の労働局またはハローワーク |
障がい者の雇用定着のため、業務をするうえで必要な援助や支援を行う職場支援員を雇用、または委託した事業主に対し助成されるものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 職場介助者等助成金(職場介助者の配置又は委託助成金) |
| 支給要件 | 対象障がい者が主体的に業務を遂行するために職場介助者の配置または委嘱をおこなわなければ雇用継続を図ることが困難な事業所の事業主であること |
| 支給額 | 配置1人あたり15万円/月、委嘱1回あたり1万円・年間150万円を上限とし、配置または委嘱に要した賃金は費用の4分の3を支給 |
| 対象障がい者 | 重度視覚障がい者または重度四肢機能障がい者で、雇用継続のために職場介助者の配置または委嘱が必要だと認められる方 |
| 支給期間 | 起算月から起算して10年の期間のうち、当該職場介助者を配置または委託している期間 |
| 注意点 | 対象となるのは申請後の措置。申請前からおこなっている措置は対象外 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
参照:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED|障害者雇用納付金関係助成金支給要領
中途障がい者に対し、療養後の職場復帰において本人の能力にあった職務の開発や職場環境の整備などを実施した事業主に支給されます。事故や病気により障がいを負った雇用者の職場復帰の推進や雇用の継続が目的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金) |
| 支給要件 |
以下のすべての要件に該当する事業主
|
| 支給額 | 中小企業の場合6万円/月、中小企業以外の場合4万5,000円/月を支給 |
| 対象障がい者 | 常時雇用されている労働者のうち、身体障がい者・精神障がい者・難病等患者・高次脳機能障がいがある方で、医師の意見書により1ヵ月以上の療養のための休職等が必要とされている方 |
| 支給期間 | 1年間 |
| 注意点 | 対象となるのは申請後の措置。申請前からおこなっている措置は対象外 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
障害者雇用納付金制度は、障がい者の法定雇用率を達成している企業に調整金や報奨金を支給するものです。常時雇用している労働者が100人を超え法定雇用率よりも多く障がい者を雇用している企業については調整金、常時雇用労働者が100人以下で障がい者を一定数以上雇用している企業については報奨金を支給します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 障害者雇用納付金制度 |
| 支給要件 |
|
| 支給額 |
【調整金】雇用率を超えて雇用している障がい者数1人あたり2万9,000円/月(ただし支給対象人数が年120人を超える場合、1人あたり2万3,000円) 【報奨金】一定数を超えて雇用している障がい者1人あたり2万1,000円/月(ただし支給対象人数が年420人を超える場合、1人あたり1万6,000円) |
| 対象障がい者 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 |
| 申請手続先 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED 各都道府県支部 |
人材開発支援助成金は、労働者のキャリアアップを促進するための助成金です。中でもこのコースは、障がい者が仕事において必要な能力を得るための教育訓練を行う施設を設置・運用する企業を対象としています。
なお、人材開発支援助成金は令和6年度から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金へ移管し、障害者能力開発助成金となりました。障害者能力開発助成金については、以下よりご確認ください。

障がい者雇用の補助金は、有無も含め、自治体によってさまざまです。ここでは、補助金の例と対象地域、概要などをご紹介します。
岡山県高梁市などで導入されている制度です。高梁市では、障害者雇用促進補助金に以下の内容の補助金や奨励金を含めて設定しています。
支給決定を受けた特例子会社に、障がい者雇用1人につき1年目は月額1万円、2年目は月額7,000円、3年目は月額4,000円が支給されます。ただし、対象障がい者が特定求職者雇用開発助成金の支給対象となっている場合、対象期間については支給されません。
交付決定を受けた特例子会社に対し、市内に居住している障がい者の通勤のための送迎に要した費用が交付されます。交付額は、送迎の人数や頻度により、1人あたり100円または210円です。
支給決定を受けた障がい者雇用事業所や社会福祉法人などに対し、障がい者の雇用のためにおこなった機器整備や施設整備などの費用のうち一部が補助金として支給されます。支給額は、整備に要した費用の2分の1の額が基本となります。
支給決定を受けた障がい者雇用事業所や社会福祉法人などに対し、障がい者の市内グループホームへの定住促進、または就労機会の提供をした場合に奨励金が支給されます。支給額は、障がい者1人につき1年目は月額1万円、2年目は月額7,000円、3年目は月額4,000円です。
京都府で導入されている制度です。以下の2つの補助金によって構成されています。
京都府内の事業所のうち、障がい者の就労継続に必要な施設や設備の整備をおこなう事業所に対して補助金が支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 障害者雇用施設整備事業費補助金(京都府) |
| 支給要件 |
以下の要件のいずれかに該当すること
|
| 支給額 | 100万円を上限とし、補助対象経費の30%(15%)を支給(※カッコ内は常時雇用労働者が1,000人以上の事業主) |
| 対象障がい者 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 |
| 申請手続先 | 京都府商工労働観光部雇用推進課 |
京都府内の事業所のうち、カウンセラーの配置や管理ソフトの導入など、障がい者の就労定着に必要な支援事業をおこなう事業所に対して補助金が支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 障害者定着支援事業費補助金(京都府) |
| 支給要件 |
以下の要件のいずれかに該当すること
|
| 支給額 | 100万円を上限とし、補助対象経費の30%(15%)を支給(※カッコ内は常時雇用労働者が1,000人以上の事業主) |
| 対象障がい者 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者 |
| 申請手続先 | 京都府商工労働観光部雇用推進課 |
長野県須坂市で導入されている制度です。障がい者が作業するために必要な施設の新築や改築などに必要な費用、また作業に必要な機械や備品の改造をするために必要な費用のうち、50万円を限度とし2分の1以内の額が補助されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 障害者作業施設等整備事業補助金(須坂市) |
| 支給要件 | 須坂市内に事業所があり、障がい者を常時労働者として雇用していること |
| 支給額 | 50万円を限度とし、障がい者の作業施設および設備の新築や整備等に要する額の2分の1を支給 |
| 対象障がい者 | 65歳未満の身体障がい者・療育手帳の交付をうけている方・そのほかハローワークが障がい者として認めた方 |
| 申請手続先 | 須坂市産業連携開発課 |
障がい者雇用の助成金・補助金の支給までの手順は制度ごとに確認する必要がありますが、おおよその流れは以下の通りです。
ここまでご紹介したように、障がい者の雇用に関する助成金にはたくさんの種類がありますが、これらの助成金を申請する際の注意点についても2つお伝えします。
障害者雇用促進法の改正により、平成28年から、雇用分野における障がい者の差別の禁止と、職場での障がい者の支障を改善するための合理的配慮の提供が義務付けられました。
障がいの種類や程度、あるいは個々人の適性によって、業務の進め方や職場環境において配慮が必要となる場面が生じることがあります。その際は、特定の従業員へ負担が集中したり、不当な差別が発生しないような環境づくりが必要です。
障がい者を雇用する上では、障がいのある方が力を発揮しやすいよう、周囲が適切に業務を調整したり、必要なサポートをおこなったりすることが大切です。本人との対話を重ねながら業務設計を進めることが難しい場合は、関係機関に相談したり、ジョブコーチを活用したりする方法もあります。
障がい者を雇用する際には、職場のバリアフリー化など物理的な整備も重要ですが、職場全体で障がい者雇用への理解を共有することも大切です。
障害者雇用促進法においては、40.0人以上(令和7年1月時点)を雇用している事業主に対して障がい者の法定雇用率の達成を義務付けています。自社がその要件を満たしているかどうか、その実雇用率を計算する際には、いくつかの注意点があります。障がいの種類や程度、雇用形態によって、計算する際の基準が異なるからです。
まず雇用形態についてですが、所定労働時間が週30時間以上の常時雇用労働者は1人としてカウントされます。一方、所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者は短時間労働者として0.5人としてカウントされます。これが実雇用率における基本的な数え方です。
さらに、障がい者の法定雇用率の算定基礎となる身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者のうち、重度の身体障がい者、知的障がい者は1人で2人分として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合は0.5人としてカウントされます。つまり、重度の障がい者を常時雇用労働者として雇用した場合は2人、短時間労働者として雇用した場合は1人、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で雇用した場合は0.5人雇用したこととして実雇用率を計算するのです。
また、精神障がい者については、短時間労働者として雇用した場合は1人、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合は0.5人雇用したこととして計算します。実雇用率を計算する際にはこれらの点に注意し、正確な数値を算出しましょう。
カウント方法については以下の記事で詳しく解説をしています。
障がい者雇用の等級によるカウント方法の違いとは?

最後に、障がい者雇用の助成金・補助金を実際に検討する際に企業の方がよく抱く疑問・質問とその回答をご紹介します。
助成金と補助金は混合されがちですが、一番の違いはもらえる確実性にあります。
厚生労働省の説明によると、雇用関係助成金は、一定の条件を満たした場合に支給されるものとされています。基本的な交付要件に合致していれば原則として交付されるものです。障がい者雇用では、基本的には助成金が活用されます。
一方、経済産業省は補助金について、申請内容を審査し、採択された事業者に対して交付するものとしています。つまり、申請要件のほか、事業計画などに関する審査があり、採択・不採択があるということです。補助金は地方自治体が独自に展開している場合が多い制度となっています。
障がい者雇用の助成金の申請窓口は、多くは独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEED、あるいは厚生労働省、ハローワークとなります。助成金再編によって申請窓口が変わっている場合もあるので、申請前に確認しましょう。
補助金の申請窓口は、補助金を設置している各自治体の担当部署となります。ホームページなどに情報が載っているため、それを参照してください。
短時間勤務の障がい者を雇用した場合でも助成金・補助金の対象になる場合はあります。障害者短時間トライアルコースのような短時間労働に特化した助成金も存在します。これは、障がい特性などにより長時間労働が難しい労働者への配慮でもあります。自社の短時間雇用に該当する助成金・補助金があるかどうか確認してみましょう。
助成金・補助金は、月ごとに払われるものもあれば、1年に一度というものもあります。特に、施設設置等の助成金・補助金の場合は、実際に施設設置等の費用を支払ったあとに支払い費用を踏まえて申請し支給される後払いパターンが一般的です。
厚生労働省による雇用関係助成金支給要領には、助成対象となる事業主について、「事業の経営の主体である個人または法人若しくは法人格がない社団若しくは財団をいう」と明記してあります。つまり、個人事業主でも助成金の申請は可能です。
補助金については、各自治体が独自に定めているものが多いため、その基準は自治体判断になります。管轄の自治体が準備している補助金の要項を確認することで、個人事業主でも申請可能かどうか判断できます。
障がい者雇用についての相談は、申請先であるハローワーク、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構JEEDのほか、障害者就業・生活支援センターや地方労働局、自治体窓口などでも受け付けています。

この記事で解説してきた助成金について、大きく分けると、
の4種類があります。各助成金の詳細や具体的な手続きについては厚生労働省のホームページなどを参考にしてください。
補助金については自治体によって扱いが変わるため、事業所がある自治体やその周辺の地域などでどのような制度があるかを確認しておくと良いでしょう。
障がい者を雇用する事業主は、いま雇用している障がい者、あるいは雇入れしようとしている障がい者にとって働きやすい職場を作り、周囲の社員も合理的配慮をする義務があります。こうした配慮は、安全性などの向上はもちろん、生産性の向上にも繋がります。ここでご紹介した各種助成金を積極的に活用し、障がい者の雇用拡大に努めていきましょう。


2026年7月に実施される、民間企業の法定雇用率「2.7%」への引き上げについて徹底解説します。今回の改定により、障がい者雇用の義務対象が「従業員数37.5人以上」の企業へ拡大。引き上げの背景、雇用すべき人数の計算方法、未達成時の「納付金」や「企業名公表」のリスク、そして円滑に雇用を進めるための外部機関や支援サービスの活用法まで、人事担当者が今すぐ知っておくべき情報を網羅しました。

障がい者雇用は企業の義務として法律で定められており、法律に違反することは納付金...

障がい者雇用に取り組んでいる事業主の方のなかには、「もにす認定」という制度を耳...