
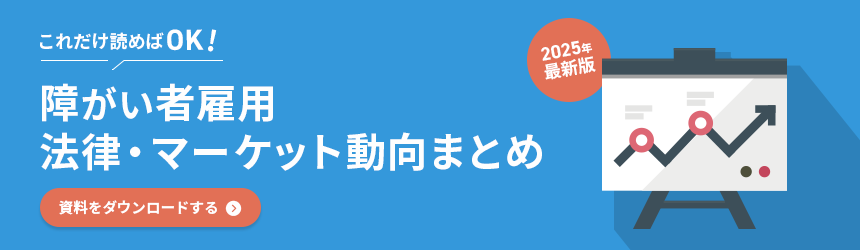
障がい者雇用に取り組んでいる事業主の方のなかには、「もにす認定」という制度を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
もにす認定は、障がい者雇用についての取組が優良な中小企業に与えられる認定で、これを受けることで低利融資の対象になるなど、さまざまなメリットがあります。
この記事では、もにす認定制度の概要や認定を受けるメリット、認定までの申請手順などを解説します。
もにす認定制度とは、正式名称を「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」といいます。その名の通り、障がい者雇用への取り組みが良い中小企業に対して、厚生労働大臣が認定を与える制度です。企業と障がい者が社会のなかで「ともにすすむ」という意味から名付けられました。
もにす認定の大きな目的は、障がい者雇用の促進です。多くの企業がもにす認定を目指すことで、中小企業全体が障がい者雇用への取り組みを強化することを狙いとしています。
もにす認定を受けた企業は、地域における障がい者雇用のロールモデルとして社名が公表されます。それにより、障がい者雇用に取り組む企業としての認知度を高め、地域全体で障がい者雇用への取り組みが推進されることを狙いとしています。
もにす認定は、厚生労働省が定める一定の認定基準をクリアすることで受けることができます。
認定されると、自治体からさまざまな優遇措置を受けられるようになります。認定マークの使用許可や認定事業所の公表など、企業のイメージアップにつながるもののほか、低利融資の対象になるなど金融面での優遇措置もあります。
厚生労働省が公開した「令和6年障害者雇用状況」の集計結果によると、従業員数43.5~100人未満の企業における障がい者の実雇用率は1.95%(前年度は1.95%)、従業員数100~300人未満の企業の実雇用率は2.19%(前年度は2.08%)でした。令和5年の法定雇用率が2.5%なので、中小企業全体の実雇用率は法定雇用率に到達していないことがわかります。
また、法定雇用率達成企業の割合は、従業員数43.5~100人未満の企業で45.4%(前年は47.2%)、100~300人未満の企業で49.1%(前年は53.3%)という結果でした。前年度と比較すると実雇用率、法定雇用率達成企業の割合ともに増加傾向にありますが、中小企業の障がい者雇用状況はまだまだ理想の水準には到達していないことがうかがえます。
もにす認定事業主になると、さまざまなメリットが得られます。ここでは主な3つのメリットをご紹介します。
もにす認定には独自の「認定マーク」があり、もにす認定を受けると、このマークを商品や広告、名刺や求人票などに表示できるようになります。これにより、障がい者雇用という社会的課題に真摯に取り組む企業としてアピールできます。
もにす認定を受けている事業主は、令和6年9月30日時点、全国で468を数えます。そのすべての事業主名と業種などの情報は厚生労働省のホームページで公表されており、知名度のアップにつながっています。
参照:厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)認定事業主」
また、ハローワークの求人票にも必ず認定マークが掲載されます。認定事業者限定の合同説明会などが開催されることもあり、採用活動の手助けにもなるでしょう。
もにす認定事業主は、「働き方改革推進支援資金」の融資を低金利で受けられます。
働き方改革推進支援資金とは、日本政策金融公庫がおこなう融資制度の一つです。非正規雇用の処遇改善や障がい者雇用などの働き方改革に取り組むための設備資金や長期運転資金の貸付をします。例えば、合理的配慮のために事業所内にスロープやエレベーターの設置を検討する場合、この設備投資のための資金が低金利で借りられ、障がい者雇用のさらなる推進につなげやすくなります。
もにす認定を受けた事業主は、以下の事業の落札などで加点評価を受けられる場合があります。
特に地方公共団体の公共調達においては、もにす認定による加点評価が勧められています。公共調達において加点がつけば公共事業を落札できる可能性が高くなり、安定した事業運営の手助けとなるでしょう。
ただし、すべての公共調達や補助事業が対象になっているわけではないため、事前に実施要項などをよく確認してください。

もにす認定には、国が定める一定の認定基準があります。基準要件は幅広いため、ここでは一部を紹介します。詳細については以下のマニュアルを確認してください。
認定申請をおこなえるのは、常時雇用する労働者が300人以下のすべての事業主です。常時雇用する労働者の数は、障害者雇用促進法に基づき以下のように数えます。
法人の種類に制限はなく、法人化していない個人事業主でも申請することが可能です。
障がい者雇用の取組についての評価は、大きく以下の3つの分野でおこなわれます。
上記のそれぞれには小項目があり、小項目ごとに点数で評価され、それぞれの小項目の合計点を算出します。すべての合計点が合格最低点に達しており、かつ3分野合計で20点以上(特例子会社は35点以上)の得点をとることが、もにす認定基準のひとつです。
もにす認定には、障がい者の雇用人数について以下の2つの基準が設けられています。
雇用率制度の対象障がい者とは、週所定労働時間が20時間以上の知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者のことを指します。また、重度知的障がい者、重度身体障がい者、精神障がい者については、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合でも対象障がい者としてみなされます。
法定雇用障害者数とは、常時雇用する労働者の人数に法定雇用率をかけて算出する人数で、1人未満は切り捨てます。令和6年5月現在の民間企業の法定雇用率は2.5%で、常時雇用する労働者が40人以上のすべての事業主は、労働者数に応じて法定雇用率以上の障がい者を雇用しなくてはなりません。
雇用率制度における雇用障がい者の人数の数え方には、以下の表のようなルールがあります。このルールに基づいて数えた障がい者の人数が法定雇用障害者数を上回ることが、障がい者雇用人数についてのもにす認定基準(1)を満たすこととなります。
(表)障がい種別の障がい者1人についての雇用人数の数え方
| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 |
10時間以上 20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |
| 重度身体障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | - |
| 重度知的障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障がい者 | 1人 | 1人(当面の間) | 0.5人 |
また、常時雇用する労働者が40人未満で、障がい者の法定雇用義務がない企業であっても、1人以上の障がい者を雇用していれば、もにす認定の申請をすることができます。この場合の「1人」は実人員での数え方となるため、0.5人カウントの短時間労働者であっても1人雇用していればOKです。
ただし、指定就労継続支援A型において雇用している以外に1人以上の雇用が必要であるため、指定就労継続支援A型を経営している事業主の方は注意が必要です。
その他の認定基準には以下のようなものがあります。
参照:厚生労働省職業安定局「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」
違反行為などについては、現在だけでなく過去にさかのぼって審査されます。申請を検討している事業主の方は、過去に認定基準から外れる出来事がなかったか、よく確認するようにしましょう。
認定申請を考えている方に向け、もにす認定の申請手続きを簡単にご紹介します。実際の申請についての不明点は、所属する都道府県労働局またはハローワークにお問合せください。
もにす認定を申請するには、以下の書類を揃える必要があります。
| 書類の名前 | 書類の内容 |
|---|---|
| 基準適合事業主認定申請書 | 事業主の氏名または名称、そのほか必要事項を記入します |
| 認定基準確認申立書 | 認定基準に該当することを申告します(評価自己採点表と障害者雇用状況報告書を先に記入すると、作成が簡単になります) |
| 障害者業務提供等事業に係る該当申告書 | 障がい者雇用をおこなっていることを申告します。障がい者の就業場所、就労する障がい者数、具体的な業務を記入します |
| 評価基準自己採点表 | 障がい者雇用の取組などの評価を自身で採点します(評価要素該当申告書を先に記入すると作成が簡単になります) |
| 評価要素該当申告書 | 障がい者雇用の取組などに対する評価の自己採点にあたって、取組がどの評価要素に該当するか具体的に申告します。評価要素に該当することを証明する書類の添付が必要です |
| 就労支援機関等による評価基準該当証明書 | 障がい者雇用の取組のうち、規定された方法によって評価できない取組について、事業主が連携する就労支援機関などから「一部の項目を除いて評価基準に該当していること」を証明してもらう書類です |
| 障害者雇用状況報告書 | 事業主における障がい者雇用の状況について報告します。申請日の前日から起算して過去1年以内に障害者雇用状況報告書を提出している事業主は再提出不要です |
| そのほか | 認定審査にあたって求められる書類を提出します |
参照:厚生労働省職業安定局「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度 申請マニュアル(事業主向け)p.15~」
様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。様式内の記入方法を参照のうえ、間違いのないように記入します。
審査にあたっては追加の書類を求められる場合もあるため、その都度対応しましょう。
申請書の提出先は都道府県労働局ですが、ハローワークを通しておこなうことも可能です。メインの事業所を管轄している都道府県労働局またはハローワークに申請書類を提出しましょう。
都道府県労働局によって、申請書類に不足がないこと、申請書の記載に漏れがないことが確認されると、申請が受理され審査がはじまります。
認定審査では、提出した書類の審査のほか、ハローワークによる訪問の審査もおこなわれます。
訪問の審査では、申告書の内容の確認のほか、障がい者雇用の取組全般について口頭でのヒアリングがされることもあります。対応する職員は取組内容をしっかりと答えられるようにしておきましょう。
取組の評価については、申請の時点では自己採点によって申告しますが、訪問審査などをとおして評価の補正が必要になる場合があります。その場合は、訪問審査後、補正の指示や申告書の再提出などのやりとりが必要になります。指示に従い、期間内に対応しましょう。
審査の結果は、認定された場合は「基準適合事業主認定通知書」、認定されなかった場合は「評価基準採点表」と「基準適合事業主不認定通知書」の送付によって通達されます。申請書が受理されてから認定の決定までは3ヵ月程度かかります。
もにす制度がはじまった令和2年以降、さまざまな業種で認定取得企業が増えています。2024年9月30日時点での認定事業主は、468社となっています。
もにす認定を取得している企業は厚生労働省のホームページで、個別の事業主名や都道府県、認定年月日、業種を確認できます。
もにす認定を取得する要件の一つに、厚生労働省が定めた評価項目で合格点以上の得点を取得することがあります。令和2年10月から令和2年12月に認定を受けた認定企業22社の得点傾向をみると、以下の項目で得点している企業が多い傾向にあります。
具体的な取組については、以下のようなものがあります。
もにす認定を受けている事業主の取組については、厚生労働省のホームページで詳しくみることができます。

もにす認定には有効期限はありません。ただし、1年に1度の障害者雇用状況報告書の提出などを通して障がい者雇用の状況について定期的に報告する必要があり、その結果、もにす認定の認定要件から外れていると判断された場合には認定取消となります。また、事業主から認定の辞退の届出を出した際にも認定は無効となります。
一度認定されたからといって安心するのではなく、継続して障がい者雇用に積極的に励み、常により良い取組を目指していくことが大切です。
もにす認定を受けることにはさまざまなメリットがあり、企業のイメージアップにもつながります。また、認定基準を満たすということは、障がいの有無に関わらず、その企業で働くすべての方にとって働きやすい環境を作るということです。働きやすい労働環境が作られることで、働く方は仕事に楽しみややりがいを感じやすくなり、業務効率の向上にもつながっていきます。
障がい者雇用に積極的に取り組んでいる事業主の方は、企業全体の環境や業績の底上げのためにも、もにす認定の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
