
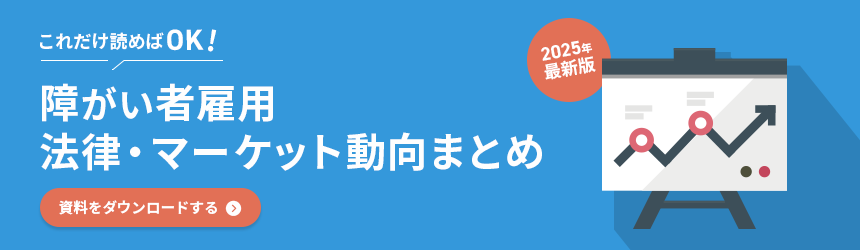
「障害者トライアル雇用」は、障がい者を原則3ヶ月間試行雇用し、適性や能力を見極め、継続的に雇用するきっかけを作ることを目的とした制度です。企業としては、労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行できるため、障がい者雇用への不安を解消することができます。
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障がい者に該当する方が対象で、障がい区分は問いません。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
障害者トライアル雇用の期間は、精神障がい者とそれ以外の障がい者によって区別されています。
障害者トライアル雇用を実施する企業には、障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、一定の条件を満たすことで、助成金が支給されます。企業はこの助成金を活用することで、コストを抑えることが可能です。
障害者トライアルコースの助成金は以下の通りです。
障害者トライアル雇用以外にも、障がい者雇用に関する助成金には様々なものがあります。詳しくは「障がい者雇用の助成金・補助金とは?種類や条件について解説」をご覧ください。
障害者トライアル雇用には、短時間トライアル雇用があります。
短時間トライアル雇用は、下記の条件に当てはまる人を雇用する場合に実施できる制度です。
短時間トライアル雇用は、週10以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始します。 その後、職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指すものとなっています。
助成金の支給額は、対象者1人当たり、月額最大4万円(最長12ヶ月間)となっており、障害者短時間トライアル雇用求人の提出が必要となります。
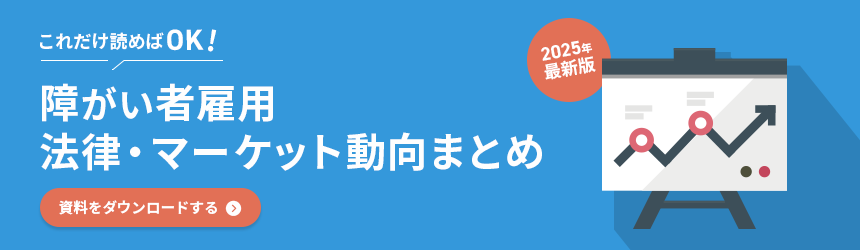
障害者雇用トライアル雇用の流れは、以下のようになります。
「障害者トライアル雇用求人」に応募し、採用が決まったら、約3~6ヶ月間の有期雇用 契約を締結します。トライアル雇用期間終了後、改めて継続雇用契約を締結します。
実施計画書:障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付してください。
支給申請書:助成金を受給するためには、障害者トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に、 事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
※ 障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合、支給申請期間が変わるため、ハローワークへの連絡が必要です。
障がい者がトライアル雇用で働くメリットは、働いてみなければわからない職場の雰囲気や詳しい業務内容を、実際に体感することができることです。社員として、その職場で働くイメージを具体的にすることができます。
せっかく就職したにも関わらず、採用後に「こんなはずではなかった」と思い、退職するケースは少なくありません。障害者トライアル雇用期間中に、仕事内容や、職場の様子を知り、必要なサポートを受けることにより、納得して働くことができます。また、トライアル雇用から常用雇用への移行している割合が※約8割ほどあることも、職場定着率が高いこともメリットといえます。
求職者中には、応募する業務の経験が少なかったり、業務未経験である場合も少なくありません。しかし、採用側もトライアル雇用という期間があることによって、ポテンシャル採用を行うことを積極的に考えることができ、採用のハードルを下げやすくなります。そのため、新しい職種や業界にチャレンジする機会が広がることにつながります。
障がい者にとっての障害者トライアル雇用の最大のデメリットは、有期雇用であることです。約8割が常用雇用に移行しているといっても、残りの2割は離職しているということになります。障がい者本人による辞退もありますが、企業側から本採用を見送られる場合もあります。
たとえ障害者トライアル雇用だったとしても、職歴として残るため、3ヵ月から1年の短期離職として扱われてしまい、次の求職活動に不利に働いてしまう可能性があります。
求職者の適性や能力を見極めた上で、雇用を決められることは大きなメリットになります。限られた面接時間だけではわからないことも、障害者トライアル雇用を実施することで、働きぶりで判断することができるので、企業に合った人材を採用しやすくなります。
時間や労力をかけて本採用しても、ミスマッチがでてしまうと、大きな負担がでますが、そのようなリスクを軽減することができます。仮に継続雇用が難しいという判断になったときでも、トライアル後の常用雇用は義務ではないので、期間が満了することによって、雇用契約を解除することが行いやすくなっています。
また、要件を満たすことによって助成金が支給されるため、採用コストを抑えながら人材採用を行うことができます。
障害者トライアル雇用はあくまで試用雇用なので、雇用する障がい者が即戦力ではないという可能性があります。また、戦力になるように知識や技術を教えても、それ以外の面で職場に馴染むことができず、本採用を見送ることもあるでしょう。その場合、もう一度障がい者雇用へ向けた取り組みをしなくてはなりません。
さらに、求人票の作成や助成金の申請などの手続きが多く、普段の業務に加えてこれらの業務をおこなうことで、社内の負担が増えてしまうというデメリットもあります。
障害者トライアル雇用を活用した人たちは、障害者トライアル雇用後も、約8割以上の方が継続雇用されています。
平成25年~27年の実績を見てみます。
平成25年 活用数3340人 継続雇用率85.2%
平成26年 活用数5058人 継続雇用率84.5%
平成27年 活用数5987人 継続雇用率85.5%
この結果を見ても、障害者トライアル雇用を活用している人数が増加しており、トライアル雇用をきっかけにして継続雇用される障がい者が増え、障害者トライアル雇用終了後にも定着していることがうかがえます。
実際に障害者トライアル雇用を活用して、精神障がい者を雇用したある医療機関の事例を見てみましょう。
ある法人では、身体障がい者を雇用したことはありましたが、今まで精神障がい者を雇用したことはありませんでした。そのため精神障がい者を雇用した経験がないため、どのような仕事内容にしたらよいのか、また職場環境を整えればよいのかを悩んでいたそうです。
障害者トライアル雇用で就職した方は、精神障がいのある統合失調症の30代の方でした。障がい特性としては、記憶力や集中力で心配なところがあること、臨機応変な対応やマルチタスクの作業に関しての苦手さがありました。
障害者トライアル雇用期間中には、事業支援として、ハローワーク等の職員の方に定期的に事業所を訪問してもらい、コピー業務や郵便物・カルテの搬送などの具体的な仕事内容を作り出すことができました。支援には、ハローワークの精神障害者雇用トータルサポーターと障害者就業・生活支援センターの職員がチーム支援として関わっています。
チーム支援からの適切なアドバイスを受けながら、社内に担当者を決めて、本人の障がい特性を職場内でも共有するとともに、休憩時間や通院日など、本人の健康面に留意した配慮をおこなうことができました。
このように障害者トライアル雇用期間中に、職場での業務や適切な配慮を行うことができた結果、障害者トライアル雇用終了後も継続雇用されています。
長期的に働ける障がい者を雇用するためにも、障害者トライアル雇用を取り入れたいと考える企業は多いでしょう。障害者トライアル雇用を実施するにあたっての注意点を4つご紹介します。
障害者トライアル雇用は障害者トライアル雇用求人にのみ適用されますので、まずは障害者トライアル雇用のための求人票を作成する必要があります。一般的な障がい者求人に応募されたものはトライアル雇用の対象にならないため注意が必要です。
障害者トライアル雇用は、障害者トライアル雇用をしている障がい者が継続的に働くことを目的にしている制度です。そのため、求人数を超えた障害者トライアル雇用を実施することはできません。求人票を作成する時点で、雇用する人数を確定する必要があります。
障害者トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うよう、ハローワークから要請が出されています。面接で実際に話すと、書類上ではわからない障がい特性やその人の雰囲気などがわかります。面接をおこなうことは、求職者だけでなく企業にとっても重要なことです。
助成金の申請は、障害者トライアル雇用終了の翌日から2ヵ月以内におこなう必要があります。実際に障害者トライアル雇用をしている期間中には助成金の支給はなく、終了後にまとめて支給されます。また、2ヵ月の期限を切れてしまうと受給対象外になってしまうため、障害者トライアル雇用が終わったらなるべく早く申請書類を提出できるように準備をしておくことが良いでしょう。
参照:厚生労働省|トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内
助成金の受給額は出勤日数によって変動します。障害者トライアル雇用の期間中に年次有給休暇などの有給休暇以外の欠勤が多いと支給額が減額になる場合もあるため、注意が必要です。
具体的には、支給対象者が1ヵ月に就労を予定していた日数のうち、実際に就労した日数の割合をAとすると、受給額は以下のように変動します。
参照:厚生労働省|トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
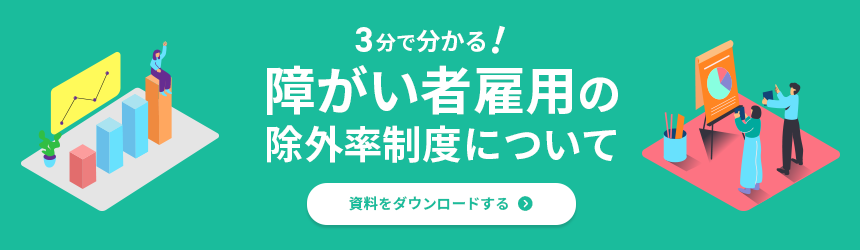
障害者トライアル雇用とはどのような制度なのか、その仕組みや企業側・求職者側のメリットを見てきました。
障害者トライアル雇用は、期間を決めて採用することができるので、企業側にとっても、求職者側にとっても、仕事や職場の様子のミスマッチを減らすことができ、結果的に職場定着につながりやすくなります。また、助成金を受けることもできますので、活用を検討するとよいでしょう。
助成金は、要件や助成金などの変更が度々あります。詳細については、労働局、ハローワークなどで確認するようにしてください。
