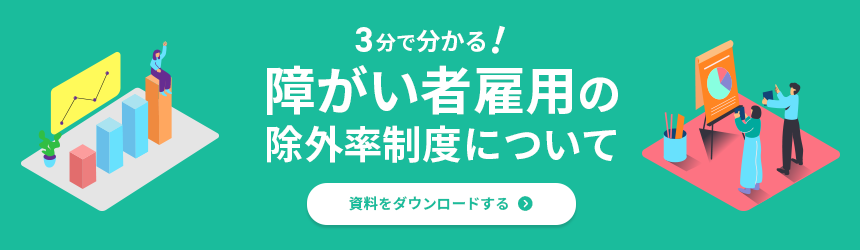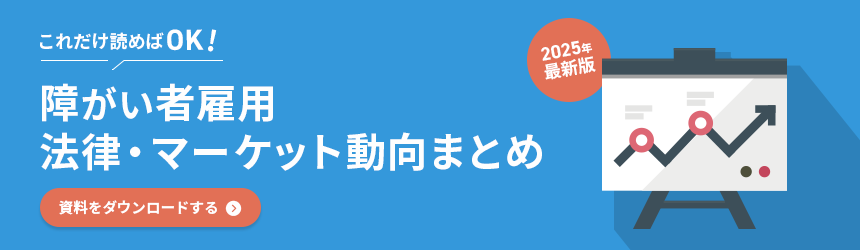
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められている制度で、法定雇用率に達していない障がい者の人数に応じた金額を納めることが求められています。
法定雇用率とは、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障がい者雇用率のことです。2024年4月からは民間企業が2.5%、国・地方公共団体が2.8%、都道府県等の教育委員会が2.7%となっています。
ここでは、障害者雇用納付金制度の目的や納付金の金額、障害者雇用納付金がどのように活用されているのかについて、見ていきます。
障害者雇用促進法では、障害者雇用納付金制度が定められています。この制度の目的は、障がい者の雇用にともなって生じる事業主の経済的負担の調整を図りながら、社会全体としての障がい者の雇用水準を引き上げることです。
障がい者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理等などを整えるために、経済的負担がともなうことがあります。そのため、これらの負担を事業主が共同して果たしていくべき責任があるという社会連帯責任の理念にたち、障がい者を雇用する事業主に対して各種の助成や援助を行う制度となっています。
障害者雇用納付金制度では、障害者雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、雇用率を達成している企業に対して調整金、報奨金などを支給するとともに、障がい者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給しています。
具体的には、法定雇用率を達成していない場合、事業主は法定人数に不足している障がい者1人あたり月50,000円を納付金として納めます。常時雇用労働者が100人超の事業主が対象です。
障害者雇用納付金として徴収されたお金は、調整金や報奨金等、また各種助成金として、障がい者雇用を進めている企業に分配されます。調整金や報奨金については、後段でさらに説明していきます。
各種助成金としては、次のような助成金があります。
障害者雇用納付金の申告義務のある事業主は、常時雇用労働者が100人超の事業主です。障害者雇用納付金の申請方法は、電子申告申請システムを活用する方法か、各都道府県の申告窓口に送付または持参する方法があります。
障害者雇用納付金の申告対象期間は、前年の4月から該当年の3月までです。また、申告期限は4月1日~5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページなどから確認してください。
事業主は、申告期限までに申告・納付ができるよう、以下の手順で申告書の作成を行う必要があります。
まず、申告の前年度(4月~3月)における月ごとの常用雇用労働者の総数を把握します。
常用雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上の労働者で、雇用期間の定めがない、または雇用期間の定めがあるが1年を超えて雇用されることが見込まれる人を指します。そのうち、週所定労働時間が30時間以上の労働者を「短時間以外の常用雇用労働者」として1人につき1カウント、週所定労働時間が20~30時間未満の労働者を「短時間労働者」として1人につき0.5カウントで計算し、常用雇用労働者の総数を算出します。
常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5ヵ月以上ある企業は申告の必要があるため、次の手順に進みましょう。
障害者雇用納付金の申告が必要だとわかったら、次は各月ごとの雇用障がい者の総数を把握します。以下のルールでカウントします。
| 障がい区分・程度 | 短時間以外の常用雇用労働者 | 短時間労働者 | 特定短時間労働者 |
|---|---|---|---|
| 重度障がい者 (身体・知的) |
1人を2カウント | 1人を1カウント | 1人を0.5カウント |
| 重度以外の障がい者 (身体・知的) |
1人を1カウント | 1人を0.5カウント | - |
| 精神障がい者 | 1人を1カウント | 1人を0.5カウント ※特例措置あり |
1人を0.5カウント |
※精神障がい者の短時間労働者には当面の間特例措置が設けられており、1人につき1カウントとして算定します(令和6年4月現在)。
表内の「短時間以外の常用雇用労働者」は週所定労働時間が30時間以上の労働者、「短時間労働者」は週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、特定短時間労働者は週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者のことを指します。
雇用障がい者の総数が確認できたら、次に企業の業種に除外率の設定があるかを確認します。
除外率とは、業務の性質上、一律に定められている法定雇用率を適用するのになじまないと判断された業種について定められているもので、これが設定されている業種については常用雇用労働者の総数から除外率相当の常用労働者数を引いて法定雇用障害者数を算出します。除外率は業種により異なり、令和6年現在は0%から80%の範囲で設定されています。
2025年4月には一律10%の引き下げが予定されており、これが実施されると除外率は0%から70%の範囲で設定されることになります。
除外率は事業所ごとに適用され、適用の判定はハローワークが行っています。適用されるかどうかわからないという場合にはハローワークに確認しましょう。
除外率の確認ができたら、納付金の額の算出をはじめます。把握した常用雇用労働者数を使い、以下の式で各月の法定雇用障害者数を算出します。
次に、算出された法定雇用障害者数と事前に確認した各月の雇用障害者数を比較します。すべての月で法定雇用障害者数を達成している場合には、納付金の納付は必要ありません。ひと月でも法定雇用障害者数を下回っていた場合、以下の式で納付金の額を算出します。
納付の必要性や納付額がわかったら、提出書類を作成します。
提出書類は、電子申告申請システムを利用して作成できます。初めて電子申告申請システムを利用する場合には、申請用のIDとパスワードを取得しましょう。
IDとパスワードを使って申請システムにログインしたら、申告申請書を作成します。手順に従って新たに作成するほか、過去のデータを利用して作成することもできます。
作成した申告書は原則としてそのまま電子申請によって提出します。提出後、翌日までにシステム上のエラーの有無などがメールで届くため、必ず確認しましょう。電子申告ができない場合には、作成した申告申請書を1部印刷して管轄の申請窓口に送付または持参により提出することも可能です。電子申告申請システム自体が利用できない場合には、所轄の申告申請窓口に相談しましょう。
障害者雇用納付金の納付方法は2種類あります。
納付金は、原則申告期日までに納付する必要があります。納付金の額が100万円以上の場合は、納付金を3分割して延納できます。延納の期日は例年、第1期が申告期日、第2期が7月末日、第3期が11月末日となっていますが、暦によって変動する場合もあるため申告書提出の際に必ず確認しましょう。
なお、延納の申請を行わなければ、100万円以上の場合であっても5月15日が納付期限となります。
(参考:障害者雇用納付金制度 Q&A)
徴収された障害者雇用納付金は、以下及び各種助成金として支給されます。
支給されるためには、申請が必要になります。
常時雇用労働者数が100人超の事業主で、法定雇用率を超えて雇用している場合に、超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額29,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
ただし、2023年の法改定では調整金の見直しがおこなわれました。2024年4月1日からは、法定雇用率を超えて雇用している人数が10人を超える場合、10人よりも多い分の調整金に対して6,000円の減額調整が適用され、1人あたり月額2万3,000円となります。
申請期限は毎年4月1日から5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
申請は、電子申請か申請書を各都道府県の申請窓口に送付または持参することで可能です。申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:厚生労働省|障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に仕事を発注した従業員100人を超える納付金申告事業主及び雇用調整金申請事業主に対しては、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。具体的には、以下の計算式で支給額を算出します。
また、法定雇用率が未達成の企業が在宅就業障がい者に仕事を発注している場合、在宅就業障害者特例調整金の額により、障害者雇用納付金の減額措置が受けられます。
申請期限は毎年4月1日から5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。申請は、電子申請か各都道府県の申請窓口に申請書の送付または持参で可能です。
申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者雇用納付金制度の概要
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
常時雇用労働者数が100人以下の事業主で、障がい者を一定数超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額2万1,000円の報奨金が支給されます。
また、2024年4月1日からは、支給対象人数が35人を超える場合、超えている分の報奨金に対して5,000円の減額調整が適用され、1人あたり月額1万6,000円となります。
申請期限は毎年4月1日から7月31日で、申請は電子申請か各都道府県の申請窓口に申請書の送付または持参で可能です。申請期限は年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:厚生労働省|障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
従業員数が100人以下の報奨金申請事業主のうち、在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に仕事を発注し、対価を支払った事業主に対しては、以下の計算式で算出される在宅就業者特例報奨金が支給されます。
申請期限は毎年4月1日から7月31日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
申請は電子申請か申請書の送付または持参で可能です。申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者雇用納付金制度の概要
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
特例給付金は、改正障害者雇用促進法(2020年4月)の制度の1つであり、短時間であれば就労可能な障がい者等の雇用機会を確保するため、週10時間以上20時間未満の雇用障がい者数に応じて支給される、納付金を財源とした給付金です。
しかし、2023年の障害者雇用促進法の改正により、重度知的・精神障がい者と精神障がい者のうち、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の特定短時間労働者について、実雇用率上0.5カウントとして算定をすることが可能になりました。この算定の変更は2024年4月1日から施行され、それにともない、特例給付金は2024年3月31日をもって廃止されました。
障害者雇用納付金を申請する際には、いくつかの注意点があります。
事業主は、申告申請の義務があるかどうかを確実に把握しましょう。
障害者雇用納付金の申告義務のある事業主は、常時雇用労働者が100人超の事業主です。各月の労働者を把握する算定基礎日に、雇用している短時間以外の労働者と短時間労働者の総数が100人を超える月が連続、または断続して5ヵ月以上ある場合は対象事業主となります。
対象にあたるかどうかについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用納付金制度記入説明書で確認してください。
納付金の申告のみであれば添付書類は必要ありませんが、常用雇用労働者数が300人以下で調整金、特例調整金の申告申請をする事業主と、報奨金、特例報奨金、特例給付金を申告申請するすべての事業主は、源泉徴収票や障害者手帳、特例措置証拠書類などの添付書類が必要となります。どの書類を添付するかは支給金の申請状況や雇用する障がい者の状況などによって細かく分けられているため、障害者雇用納付金制度記入説明書で確認しましょう。
納付義務があるにも関わらず納付期限を過ぎた場合には、改めて期限を指定された催促状が届きます。その指定期限までに納付すれば延滞金はかかりませんが、指定期限を超えてしまうと年14.5%の割合で支払いまでの日数に応じた延滞金がかかり、さらに滞納処分として財産の取り押さえが行われる場合もあるため注意が必要です。
また、納付金申告の必要があるにも関わらず未申告の場合や、申告誤りにより納付すべき納付金がある場合には、納入告知が行われます。納入告知が行われた場合、納付額の10%の額の追徴金が加算されてしまうため、申告が必要かどうかしっかりと確認し、未申告や申告誤りがないように注意しましょう。
(参考:令和5年度障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書)
アルバイトやパートタイマーであっても計上可能です。
計上の条件としては、就業から1年を超えて雇用が見込まれ、週の労働時間が20時間を超える方です。
この条件は正社員でなくても適用されます。
年度の途中で退職した場合でも、在籍期間の各月の常用雇用労働者の総数を計上する必要があります。
新型コロナウイルスに感染、または保健所から濃厚接触が疑われて休業の指示が出た場合、感染症法にもとづき就業制限や入院の勧告が行われます。
これによる休業の期間は労働時間に計上されます。
ただし、労働者が自ら休みを取るなど、上記に該当しない場合は実労働時間にカウントされません。
20時間未満であっても、カウントできる場合があります。
2023年の障害者雇用促進法の改正により、重度知的・精神障がい者と精神障がい者のうち、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の特定短時間労働者について、実雇用率上0.5カウントとして算定をすることが可能になりました。この算定の変更は2024年4月1日から施行されています。
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められている制度で、法定雇用率に達していない障がい者の人数分の納付金が求められています。ここでは、障害者雇用納付金制度の概要、目的や納付金の金額、活用方法を見てきました。
近年は、障がい者雇用でも、いろいろな制度や環境の変化を受けています。短時間であれば就労可能な障がい者等の雇用機会を確保するため、カウント方法が見直されたり、法定雇用率が、令和6年4月から2.5%に引き上げられたりしています。申請の際には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの情報を確認しながら、申請を進めるようにしましょう。