
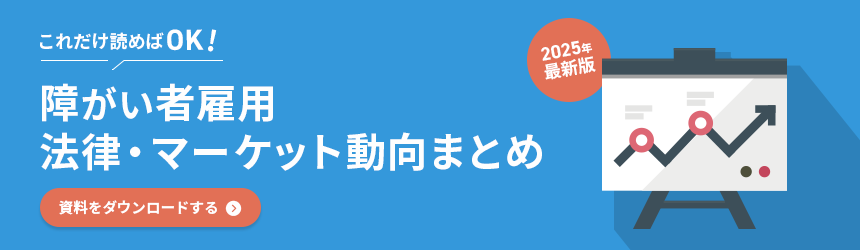
障がい者を雇用することは企業の果たすべき責任として義務付けられており、法定雇用率は段階的に引き上がり続けています。一方、法定雇用率の達成率は全体の約半数。障がい者雇用に関してさまざまな課題を抱える企業が多いのが実状です。
ここでは、企業が抱える障がい者雇用の課題と、解決のためのポイントを解説します。
障がいの有無に関わらずあらゆる立場の人たちが能力と適性に応じた職に就き、自立して生活できる社会の実現をめざすこと。これが、障がい者雇用の基本的なテーマです。
日本における障がい者雇用は、障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)によって定められています。そのなかで、障がい者を雇用することは事業主の責務として位置づけられており、様々な法的規定が存在します。
具体的には、法定雇用率が設定されており、対象となるすべての事業主は法定雇用率以上の障がい者を雇用しなくてはなりません。
法定雇用率は定期的に見直しがおこなわれ、段階的に引き上げられています。昨今の法定雇用率の引き上げ状況は以下の通りです。
| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
令和7年時点の民間企業の法定雇用率は2.5%です。一方、令和6年障害者雇用状況の集計結果によると、民間企業における法定雇用達成企業の割合は46.0%となっています。令和5年の達成割合が50.1%だったことを考えると、法定雇用率の引き上げに伴って雇用率を達成できなくなった企業が増えていることがわかります。
法定雇用率は令和8年7月には、2.7%へのさらなる引き上げが決まっており、これにより、障がい者雇用の対象事業主の範囲も拡大されます。事業主には今後より一層、障がい者雇用に積極的に取り組んでいくことが求められます。

法定雇用率未達成企業の割合を見てもわかる通り、障がい者雇用に課題を抱える企業は多いです。その課題は、採用から職場定着まで、さまざまなフェーズに存在します。
ここでは、企業が抱えやすい5つの課題について解説します。
企業は、従業員数が多くなればなるほど、より多くの障がい者を雇用しなければいけません。つまり、事業の拡大による雇用者数の増加と障がい者雇用への取り組み強化は、切っても切れない関係にあります。
法定雇用率を達成できず不足数が大きい場合、行政指導の対象となり、、その状態が続くと企業名公表などの行政措置がとられます。これは企業にとって大きなデメリットです。この事態を回避するためにも法定雇用率は必ず達成したいものですが、特に法定雇用率の引き上げによって新たに障がい者雇用義務が発生した企業にとっては、障がい者雇用は初めての取り組みとなるため、その達成は非常に難しいものとなります。
障がい者雇用に取り組むにあたっては、まず採用段階でいくつかの課題があります。
採用の際には、適切な人材を確保するために求人票を出し、応募を募るという手順があります。実はこの段階で困難を感じるという企業は少なくありません。
採用人数の目標達成のために候補となる人材を集めることを母集団形成といいますが、この段階で自社とマッチする応募者の割合を高めることが、採用活動においては重要となります。しかし、障がい者雇用のノウハウのない企業がこれを実現することはなかなか難しいものです。そもそも応募が集まらず、少ない応募のなかから、ミスマッチの人材でありながらやむを得ず雇用することもあります。
結果として、継続した雇用が実現せず、早期の退職により再度採用活動をしなくてはいけないという悪循環に陥る恐れがあります。
障がい者を雇用するにあたっては、配属する部署を決め、適性を踏まえた業務を考える必要があります。
しかし、障がい者雇用のノウハウがない場合、この業務の設計でつまずくこともよくあります。障がい者雇用の具体的なイメージがつかめておらず、どの部署に配属し、どのような業務を任せられるか想像できないためです。
また、業務を設計するためには、既存業務を洗い出し、配属部署の理解を得る必要がありますが、その理解の醸成も直面しやすい課題です。
職場環境・受け入れ体制についても考えるべき点は多くあります。
段差をなくす、エレベーターを設置するなど、目に見えるバリアフリーは想像しやすいでしょう。しかし、知的障がいの方や精神障がいの方に対しての職場環境の整備はイメージしにくい場合もあるかもしれません。
実際、障がい特性に応じて求められる環境整備はさまざまです。整理整頓をしっかりして作業導線や物の位置をわかりやすくすること、写真や図を多く取り入れた業務マニュアルを作ることなどはよく挙げられます。個々の特性に応じて、業務に集中できる環境を把握しておくことが重要です。
また、上記の例が場所としての環境だとすると、受け入れ体制は人としての環境整備であり、障がい者雇用に対する社内理解を深めることが非常に重要です。障がい者雇用に取り組むメリットや目的に対する理解が浅いと、配属後のコミュニケーションへの不安が社員の間に広がる恐れもあります。
障がい者雇用は、採用して終わりというわけではありません。採用までたどりついたら、そこからは継続雇用を目指していく必要があります。
一方、障がい者の定着率は低いのが実状です。2017年に障害者職業総合センターが実施した「障害者の就業状況等に関する調査研究」の報告書によると、障がい者雇用全体に対する雇用1年後の定着率は58.4%。社員数50人未満の企業においては1年後の定着率が46.9%となっており、半数以上の障がい者が離職している結果となりました。
厚生労働省が発表した「平成25年度障害者雇用実態調査」の結果によると、障がい者の離職理由としては以下のようなものがあげられています。
これらは、労働環境や仕事内容などへのヒアリングといった入社後のサポート不足が原因のひとつとして考えられます。また、障がい者雇用枠で採用後、キャリア形成や成長支援などをどの程度おこなっていくかという点にも課題があることがうかがえます。

障がい者雇用には、企業が直面するさまざまな課題があります。しかし、障がい者雇用は企業の義務であるため、課題があるからといって後回しにするわけにはいきません。また、障がい者雇用への効果的な取り組みは、企業に大きな利益をもたらす可能性があります。
実は、障がい者雇用の課題はいくつかのポイントを押さえることで解決しやすくなります。ここでは、障がい者雇用の課題解決に向けたポイントを解説します。
まずは全体的な雇用計画の見直しをおこないましょう。雇用計画は、障がい者雇用の基盤となる大事な部分です。採用要件や採用目標を明確にし、母集団形成をしっかりと実行します。
必要に応じて採用チャネルの見直しもおこないます。一般的に活用されるハローワークのほか、障がい者雇用専用の人材紹介や合同説明会など、採用の手段は複数あります。福祉事業所や特別支援学校などの就労支援機関と連携することも効果的です。
雇用計画をしっかりと固めて実行すれば、採用後のミスマッチを回避しやすくなり、職場定着も期待できます。
障がい者の離職理由のひとつに「職場の雰囲気・人間関係」が挙げられていることからもうかがえるとおり、障がい者の職場定着に社内理解は必要不可欠です。実際に障がい者の雇用が始まるまえに、土壌づくりとして社内理解の促進を図りましょう。
社内理解のためには、社員研修をおこなうことも効果的です。障がい者雇用の目的やメリット、障がい者と一緒に働くうえで必要な配慮などの理解を深めます。特に初めての障がい者雇用の場合は、外部講師を招く、社外セミナーに社員を参加させるなど、社外で活用できるものを取り入れていくことで効果的な社内理解を醸成することができます。
また、実際に障がい者と関わる機会をつくることも非常に重要です。障がい特性は、障がい区分ごとではなく、一人一人異なります。また実際に関わることで、多様性を受け入れるきっかけとなります。
大切なことは、障がい者雇用に参画する意識を社員一人一人がもつことです。雇用前だけでなく雇用後も継続的に研修などを取り入れ、自らが参画する意識を全員が保てるようにしましょう。
障がい者雇用に向け、適切な方法で業務の設計をおこないます。
まずは社内のさまざまな職務をリストアップし、そのなかで障がい特性があっても対応できそうな職務を選定します。そこから実際の業務をタスク単位にまで整理し、障がい者が従事できる業務を特定していきます。特定した業務を組み合わせることで、障がい者が従事する職務を構成できます。
この際、障がい者のサポート役となる社員の配置もおこないましょう。この社員は、業務面のサポートのほか、働くうえでのさまざまな悩みや求めたい配慮の相談役にもなります。
長期にわたって働けることが理想的な障がい者雇用の姿ですが、定着のためには社内のサポート体制が重要です。障がい者のサポート役となる社員のほか、雇用管理の担当者など複数の担当者を配置し、定期的な面談をおこないましょう。
面談では、職場環境は適切か、必要な配慮はないかなどの確認のほか、業務についての満足度・充実度なども確かめましょう。業務量が多い・業務が難しいと感じている場合は無理のない範囲で業務を調整し、仕事に物足りなさを感じている場合にはキャリアアップを目指せる体制を整えることも求められます。
定着支援においては、サポートする社員同士の横の繋がりも重要です。ひとりの担当者に任せきりにするのではなく、社内で分業して複数の担当者を配属します。また、管轄のハローワークなどの公的相談機関などに相談することで、企業の状況に応じた支援を受けることもできます。障がい者本人と社員、雇用主、専門機関などが一体となって障がい者雇用に取り組んでいくことで、職場定着が実現します。
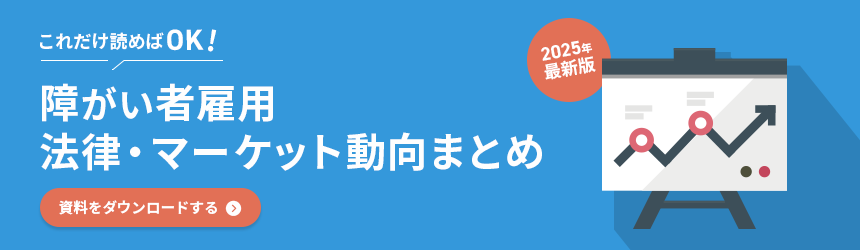
解説した通り、障がい者雇用の課題はいくつかのポイントを押さえることで解決できます。しかし、さまざまな理由から自社内での課題解決が難しい場合もあるでしょう。その場合は、障がい者雇用支援サービスを活用することもひとつの方法です。
エスプールプラスでは、貸農園を活用した障がい者雇用支援サービスを提供しています。企業がエスプールプラス所有の農園を借り、その農園を障がい者の雇用の場として活用する仕組みです。現在、日本全国で約700社、5,000人以上の障がい者がエスプールプラスの農園で業務にあたっています。1年後の定着率は92%と非常に高い水準です。
障がい者雇用と農園は、実は非常に相性のよい組み合わせです。特に知的障がいのある方は、特別支援学校などで野菜作りの経験がある方も多く、親しみのある作業となります。知的障がい以外の障がいのある方にとっても、自然に触れあうことは心身のリラックスに繋がり、楽しくやりがいを持って業務にあたれます。障がい者雇用仕様の農園なので、職場環境も安心です。
全国55か所以上に屋内型・屋外型の農園を有しており、既存の拠点と近い場所で農園を運営できることも、エスプールプラスの農園の特徴のひとつです。本社や支店と積極的に交流できる距離感で、障がい者自身が会社の一員としての誇りをもちながら働けるうえ、農園以外で従事する社員は育った野菜を福利厚生として受け取ることや、農園での障がいのある社員との交流を通して多様性の理解が促進され、ノーマライゼーション意識の向上にも繋がります。
障がい者雇用は、企業の社会的責務の遂行だけでなく、会社の長期成長に欠かせない取り組みです。しかし、そこにはさまざまな課題があり、思った通りの取り組みができていない企業が多いのも事実です。
課題の解消にあたっては、雇用計画の見直しのほか、社内理解の促進や業務設計、定着支援の取組も重要です。これらを見直しつつ、必要に応じて障がい者雇用支援サービスを活用することも検討しましょう。
自社の状況と照らし合わせながら、障がい者雇用の最適解を探ってみてください。


世界的に関心が高まっているダイバーシティ経営。自社にこの経営戦略を取り入れたい...

この記事では、「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の基本的な意味から、DE&Iとの違いまでを解説します。労働人口の減少やイノベーション創出といった社会的な背景からD&Iがなぜ重要視されるのか、そして企業がD&Iに取り組むことで得られる人材不足の解消や企業ブランド向上などの具体的なメリットを掘り下げます。さらに、D&Iを推進するための具体的な取り組み例と、実践的な5つのステップを紹介します。

この記事では、企業経営において重要性が増している「ダイバーシティ(多様性)」について、その基本的な意味から、なぜ今注目されているのかを解説します。ダイバーシティを推進することが企業にもたらす具体的なメリットや、推進する上での課題、そして実際に取り組むためのポイントを分かりやすくまとめています。